隠居の思ひつ記
高崎生まれの高崎育ち 迷道院高崎が高崎の歴史を知って 高崎を思ふ
2024年12月25日
隠居の控帳 バターの話・巡礼の話
「ボブという名の猫」という映画を見た。

ストリート・ミュージシャンのホームレス青年が、一匹の野良猫と出会い、困難を乗り越えていく奇跡を綴った実話。
クリスマスの日、青年は猫の餌を買いに、行きつけのコンビニエンスストアへ行く。
その日は店主の息子の命日だった。
青年は「メリークリスマス」と言わず、「僕は仏教の考え方やカルマを信じている」と言う。
すると店主は、「あー、カルマか」と言ってこんな話を始める。

また、不運なことが続き落ち込む青年に、店主は「現実を受け入れるしかない」と言い、「どうやって?」と問う青年に、こんな話をする。
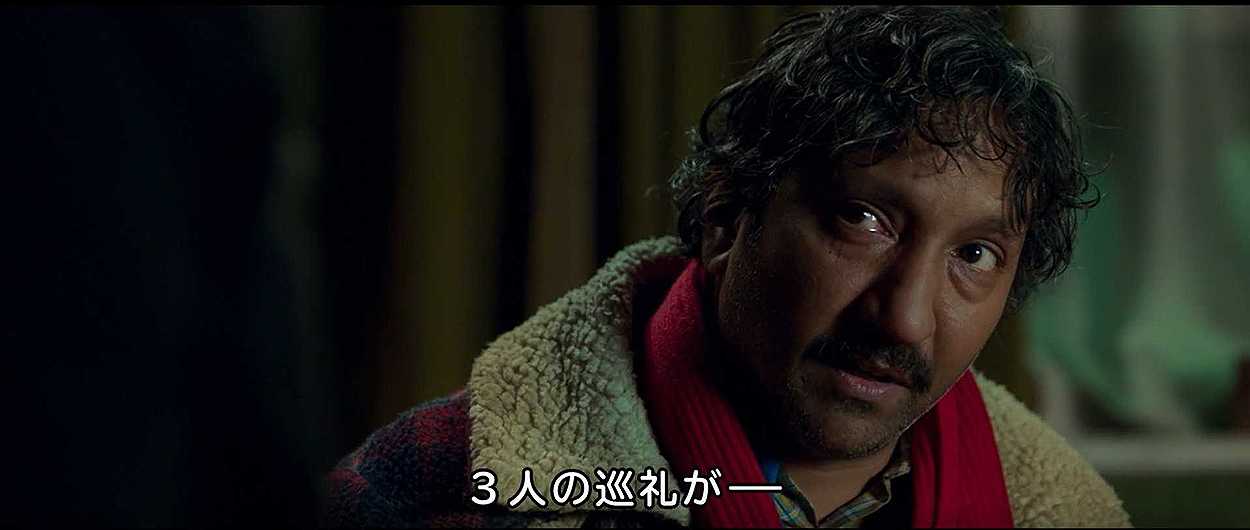
なるほど。

ストリート・ミュージシャンのホームレス青年が、一匹の野良猫と出会い、困難を乗り越えていく奇跡を綴った実話。
クリスマスの日、青年は猫の餌を買いに、行きつけのコンビニエンスストアへ行く。
その日は店主の息子の命日だった。
青年は「メリークリスマス」と言わず、「僕は仏教の考え方やカルマを信じている」と言う。
すると店主は、「あー、カルマか」と言ってこんな話を始める。

| あるところに農民がいて、商店主から毎月1キロのバターを注文された。 | |
| 引き換えに商店主が払うのは、小麦粉と豆そして1キロの砂糖。 | |
| ある日、商店主がバターを量ると900gしかなくて、商店主は激怒した。 「警察に突き出すぞ!」 |
|
| 農民は言った。 「自分は貧しくて、はかりを買えない。だから1キロのもの(商店主が払った砂糖)で量った」 |
|
| いい行いは報われる。ズルすると・・・(バターが減る)」 |
また、不運なことが続き落ち込む青年に、店主は「現実を受け入れるしかない」と言い、「どうやって?」と問う青年に、こんな話をする。
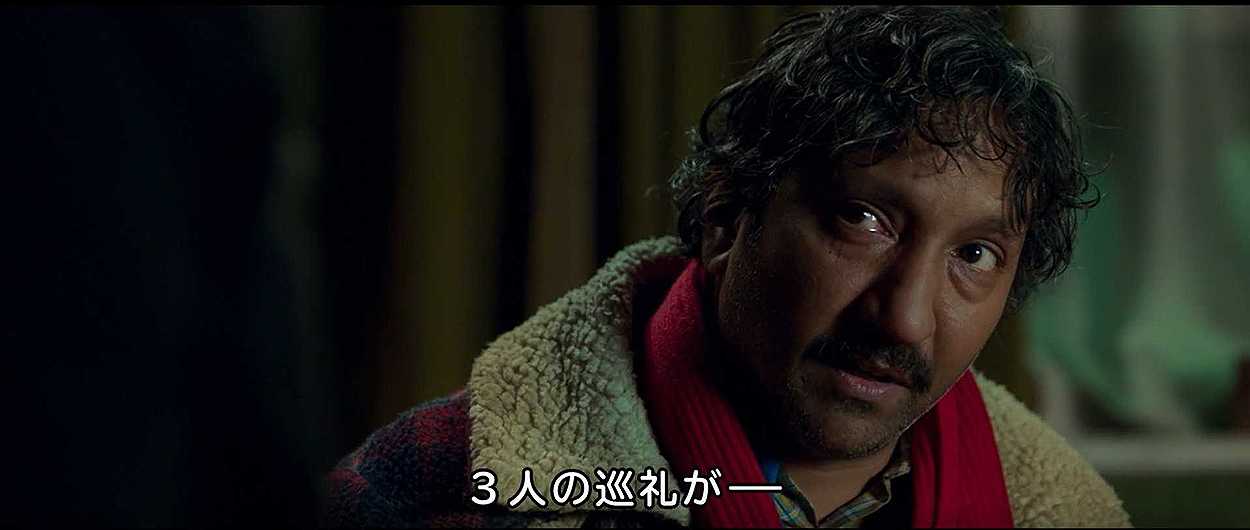
| 三人の巡礼が聖地を目指した。 三人とも悲しみを抱え平和と新しい道を求めてた。 |
|
| 三人とも、袋を2つ背中と前にぶら下げてた。 | |
| 一人目は背中の袋に人生のいいことを入れた。希望や感謝だ。 前の袋には悪いことを詰めた。悲しみ、罪、悪い思い出。 それが起きた意味を考えるためだが、それは無意味だった。 そのせいで前に進めなかった。 男は旅をやめた。 |
|
| 二人目の男は、いいことを前の袋に入れ、人にも見せた。 背中には悪いこと。すごく重かった。 足が進まず、この男も旅をやめた。 |
|
| 三人目もいいことを前の袋に入れた。 でも、ある考えがひらめいた。おかげでどんどん歩けた。 背中の袋に悪いことを入れ、袋に穴をあけたんだ。 悪いことを道に落としていった。 聖地にちゃんと到着した。 |
なるほど。
2024年12月21日
米寿観音と群馬独立
去る11月27日、群馬音楽センターで「高崎白衣大観音 米寿記念シンポジウム」というのが開催されました。
12月に入ってから、新聞各紙にその様子が掲載されました。
私も聴講しに行ってたんですが、正直、ちょっと期待外れでした。
いや、丁野朗氏の基調講演は、なかなか素晴らしいものでしたよ。
ですが、その後のパネルディスカッションが物足らなかった。
地元パネラーの視野があまりにもスポット的だな、と感じました。
白衣大観音をどうにかしたいと思ったら、それを取り巻く参道商店街や清水寺や染料植物園など、観音山全体をどうにかしなければという視点が必要だと思います。
さらに、観音山全体をどうにかしたいと思ったら、高崎全体をどうにかしないといけないでしょう。
それも、歴史という時間軸を意識して。
丁野氏の指摘は、そのことを言っているのでしょう。
なーんて思っていた時、こんな本に出会いました。

題名が面白い。
「群馬が独立国になったってよ」
中身はもっと面白い。
奇想天外、痛快無比!
深謀遠慮、気宇壮大!
ユーモラスな筆致で、現代日本の問題点とその処方箋が示唆されています。
たぶん著者は普段から、それらについて深く考えているのだろうな、と思わされます。
その処方箋は、白衣大観音についても、観音山についても、音楽センターについても、高崎の町についても有効なものだと考えます。
僭越ながら、ぜひとも、みなさんに読んで頂きたい一冊として、ご紹介申し上げました。
12月に入ってから、新聞各紙にその様子が掲載されました。
私も聴講しに行ってたんですが、正直、ちょっと期待外れでした。
いや、丁野朗氏の基調講演は、なかなか素晴らしいものでしたよ。
ですが、その後のパネルディスカッションが物足らなかった。
地元パネラーの視野があまりにもスポット的だな、と感じました。
白衣大観音をどうにかしたいと思ったら、それを取り巻く参道商店街や清水寺や染料植物園など、観音山全体をどうにかしなければという視点が必要だと思います。
さらに、観音山全体をどうにかしたいと思ったら、高崎全体をどうにかしないといけないでしょう。
それも、歴史という時間軸を意識して。
丁野氏の指摘は、そのことを言っているのでしょう。
| 「 | 観光は地域の『物語』を消費すること。 |
| 地域固有の地形や地勢、歴史、文化など多様な資源を物語りでつなぎ伝える。 | |
| そのための仕組みや人材育成が必要。」 |
なーんて思っていた時、こんな本に出会いました。

題名が面白い。
「群馬が独立国になったってよ」
中身はもっと面白い。
奇想天外、痛快無比!
深謀遠慮、気宇壮大!
ユーモラスな筆致で、現代日本の問題点とその処方箋が示唆されています。
たぶん著者は普段から、それらについて深く考えているのだろうな、と思わされます。
その処方箋は、白衣大観音についても、観音山についても、音楽センターについても、高崎の町についても有効なものだと考えます。
僭越ながら、ぜひとも、みなさんに読んで頂きたい一冊として、ご紹介申し上げました。
2024年09月29日
隠居の控帳 石破氏湛山になれるか
【湛山語録】(石橋湛山記念財団HPより)
| 「政治家の私利心」 | ||
| 人間は誰でも私利心をもっている。自分はもっていないと云ったら嘘になる。 | ||
| しかし政治家の私利心が第一に追求すべきものは、財産や私生活の楽しみではない。 | ||
| 国民の間からわき上がる信頼であり、名声である。これこそ、政治家の私利心が、何はさておき追求すべき目標でなければならぬ。 | ||
| そうでないなら、政治家をやめてほかの職業にかわるがいい。 | ||
| 「同情は我と彼を融合する」 | ||
| 私はかねて、人生の事はただ理屈だけでは理解できぬと考えてきた。 | ||
| 理屈は我と彼とを離隔し、同情は我と彼を融合する。 ここでいう同情とは、相手に憐憫の情をいだくことではなく、相手の立場を理解する努力を怠らないことだ。 |
||
| これは人生のことすべてに通ずるものであり、国と国とのつき合いでも例外ではない。 | ||
| 他人の好意を求める者は、自らこれを受けるに足るだけの行為を示さねばならぬ。外交関係でも同様だ。 このことを常に心してもらいたい。 | ||
2024年08月31日
隠居の控帳 石橋湛山
◆湛山の「小日本主義」(石橋湛山論説「一切を棄つるの覚悟」)
◆終戦処理費の削減(保阪正康著「石橋湛山の65日」より)
| 「 | 石橋にとって、戦争の精算を行うという意味では、勝者や敗者の区別はなかった。 GHQの日本占領において使われる諸経費は、終戦処理費の名目で一般会計予算から支出されるのであったが、石橋はこの削減にももっとも積極的になった。 これが因となってGHQとの関係がこじれていった。(略) |
| もとよりこの終戦処理費は、賠償の意味もあった。 日本に駐留するGHQの宿泊施設、その軍事的駐留費などが、日本の財政を圧迫するのは目に見えていた。 石橋はもともと戦後の日本社会にインフレが起きるとするなら、第一次大戦後のドイツと同様に過大な賠償金によるとの持説があり、それを財政の責任者としてもっとも恐れていた。 |
|
| 大蔵大臣に就任して四カ月ほど経て、石橋はこの終戦処理費について大蔵省の立場から具体的な調査を行ってみた。 | |
| すると進駐軍の各種工事は外務省のルートで行っていて、まったく監督が行き届かず予算の使い方が杜撰なことが分かった。 地方では、地方に駐屯する進駐軍が地元業者と直接交渉を行って勝手に工事を進めているのである。 いずれのケースでも業者が税金をくいものにしている実態が浮かびあがってきた。 こうしたムダの中には、将校の宿舎やゴルフ場などの新設も含まれていた。 『こんな状態じゃ日本の財政は日米双方のとんでもない連中からくいものにされていくだけじゃないか』 |
|
| 石橋は怒った。そこでGHQ側に自らがまとめた要求をつきつけたのである。 将校用のゴルフ場など可及的速やかに工事をやめなければならないものもあった。 進駐軍の面々に大蔵大臣としてこれだけのことは守って欲しいと強硬に要求をつきつけた。 ムダな工事をやめさせると同時に、全国に散在する多くの工事を改めて査定し、予算のムダづかいを防いでいった。 |
|
| 『われわれの、その時の計算では、少なくとも平均二割の削減を行い得る』と考えていた。 こういう英断は、そのころの絶大な権力者であるGHQに対して真っ向から、敗戦国とはいえ正論をぶつけたことになり、それはまさに気骨の士の意地でもあった。 |
|
| 石橋自身はこの終戦処理費の削減は何も不当なことを行ったわけではなく、財政の専門家としてあたりまえのことをあたりまえとして行ったに過ぎないと信じていた。」 |
◆公職追放判定基準(保阪正康著「石橋湛山の65日」より)
| A項: | 戦争犯罪人 |
| B項: | 職業陸海軍職員 |
| C項: | 極端な国家主義団体または秘密愛国団体の有力分子 |
| D項: | 大政翼賛会、翼賛政治会および大日本政治会の活動における有力分子 |
| E項: | 日本の膨張に関係した金融機関および開発機関の職員 |
| F項: | 占領地の行政長官等 |
| G項: | その他の軍国主義者および極端な国家主義者 |
◆「私の公職追放に対する見解」(舟橋洋一著「湛山読本」より)
| 中央公職適否審査委員会 御中 昭和22年5月12日 石橋湛山 |
||
| 1. | 私がG項該当者として公職から追放されるというようなことは、夢にも私が想像しなかったことである。 | |
| 2. | 私は東洋経済新報の編集者兼社長であった責任によって、公職から追放されなければならないのであり、その理由は「アジアにおける軍事的および経済的帝国主義を支持し、かつ日本国民に対し、全体主義的統制を課することを主張した」ことにあると言うのである。 しかし、私は東洋経済新報に対するこのような判決には絶対に服従することができない。 |
|
| 3. | 東洋経済新報が、終始一貫してすべての形の帝国主義と全体主義とに反対し、あらゆる戦争を拒否し、枢軸国との接近の危険を主張し、労働組合の発達に努力したことは、同誌を知る日本国民が広く一般に知っていることである。 このことについては、たとえ私の政敵であっても、その者が正直である限り、断じて否定しないと考える。 |
|
| 4. | 東洋経済新報社は、日本における自由主義の本山として一般に認められ、ために同社と私は戦時中、非常に大きな圧迫を受けた。 | |
| 5. | 私が多くの財政的損失を顧みず、昭和9年5月から日本文の東洋経済新報のほかに、英文のそれを発行した目的は、それによって日本の実情をありのままに外国に伝え、険悪になりつつあった国際関係の改善に微力を尽くすことであった。 | |
| 6. | 言うまでもなく、東洋経済新報は定期刊行物である。 したがってその発行される時期の経済、政治、社会の情勢を正しく読者に伝え、彼らに客観的批判の材料を提供する必要がある。 私はそのような目的から、私とまったく正反対の主張をする者の意見も、しばしば誌上に掲載した。しかし、その目的は、それらの主張を宣伝することではなく、逆にそれらがいかに不合理であり、虚偽であるかを読者に知らせるためであった。 |
|
| (略) | ||
| 13. | 東洋経済新報と私とは戦時中、自由主義であり、平和主義であり、反軍的であるとして圧迫を受けた。 にもかかわらず、今はそれとまったく反対の宣告を受け、私は公人としての生命を絶たれようとしているのである。 果たしてどちらが正しいのか。 貴委員会が速やかに正当なる判決を行われることを要求する。 | |
日本側の中央公職適否審査委員会は、昭和22年5月2日、吉田茂内閣の蔵相だった石橋湛山については「該当せず」との判定を下しており、吉田茂首相もそれに同意していた。
しかし、GHQはホイットニー民生局長名で湛山を追放すべしと命令した。(湛山読本)
◆公職追放後の湛山
| 昭和22年 | 11月 | 自由思想協会設立 |
| 昭和26年 | 6月 | 公職追放解除 |
| 昭和27年 | 9月 | 反党活動を理由に自由党を除名 |
| 10月 | 衆院選挙に当選 | |
| 12月 | 自由党復党承認 | |
| 昭和28年 | 3月 | 鳩山派自由党に入党 |
| 11月 | 自由党に復帰 | |
| 昭和29年 | 11月 | 日本民主党最高委員に選任 |
| 12月 | 鳩山内閣通産大臣に就任 | |
| 昭和31年 | 12月 | 自由民主党大会において総裁に選出 内閣首班に指名 石橋湛山内閣成立 |
◆湛山の「総裁選」(保阪正康著「石橋湛山の65日」より)
| 午前11時43分から新総裁を決定する投票が始まった。 単記無記名で衆参両議院の議員、それに地方代議員の順で行われた。 その結果は次のようになった。 岸信介 223票 石橋湛山 151票 石井光次郎 137票 |
|
| 過半数の256票を獲得する者がなく、岸と石橋の間で決選投票が行われることになった。(略) | |
| 午後0時30分すぎに、決選投票に入り午後1時には投票も終わり、すぐに開票に入っている。 この開票時にひとつの政治ドラマがあった。 選挙管理委員でもあった石田がのちに著書にも書き、新聞記者にも語ったために知られることになるのだが・・・ |
|
| 管理委員は壇上で集計を行う。石田はその集計結果を見ると岸票が251、そして石橋票は250になる。 わずか1票差である。石田の表現では「思わず目の前が暗くなる」という状態だった。 ところが隣を見ると三木武夫派で石橋支持の選挙管理委員井出一太郎がふるえる手で残りの投票用紙をにぎっている。 |
|
| 「君、その手の中は石橋票か・・・何票ある?」 「8票だよ」 石田は内心の笑みを隠して、議長席に近づいた。 「議長、この際ちょっと休憩したらどうですか」と砂田の耳元で囁いた。砂田は岸支持である。 砂田は、石田がそういうのであれば石橋が敗れたに違いないと判断して、「いや休憩はしない」と石田の申し出をはねのけた。 |
|
| 石田は一世一代の大芝居に勝ったと実感した。 もし休憩していたら、そして岸が負けているとわかったら、投票用紙の中には無効投票があるとの声が起こったりして、結果はどうなったかわからなかったと、石田は認めている。 |
|
| 砂田は茫然とした表情で、投票結果を発表した。(略) 石橋湛山 258票 岸信介 251票 無効投票 1票 |
|
| 会場にはどよめき、萬歳の声、さらには複雑なうめき声も発せられた。 大方の者は、岸が鳩山の後継者になるのだろうと想定していたのだが、その実態はまったく異なった形になったのである。 |
◆湛山内閣の「五つの誓い」
| 1. | 国会運営の正常化 |
| 2. | 政界及び官界の綱紀粛正 |
| 3. | 雇用の増大 |
| 4. | 福祉国家の建設 |
| 5. | 世界平和の確立 |
| 「 | 石橋湛山内閣の政策方針をまとめると、日本の高度経済成長の道筋を示した積極財政政策、親共産圏・脱安保体制の独立自主外交、および軽武装再軍備の三点である。」 |
(姜克實著「石橋湛山」より)
2024年08月10日
隠居の控帳 鬼
日課の朝散歩。
携帯ラジオから流れる仲代達矢さんの話が、心に響いた。
朗読していた言葉は、春日太一著「鬼の筆」の文中、脚本家・橋本忍が映画「南の風と波」(1961年、監督も橋本自身)の脚本を書くにあたり、創作ノートに記した文章の主要部分。
全文は以下。
春日太一は、橋本忍の作品についてこう述べる。
橋本自身もまた、たくさんの「鬼」と遭遇する。
「鬼」はこの世に無数にいるらしい。
「8月は 6日 9日 15日」と言う。
「戦争」という名の、人間が造りだした「鬼」が、すぐ近くまでやって来ているような気がする。
石を積もう、石を。
「鬼」が崩しきれぬほどの、たくさんの石を。
携帯ラジオから流れる仲代達矢さんの話が、心に響いた。
朗読していた言葉は、春日太一著「鬼の筆」の文中、脚本家・橋本忍が映画「南の風と波」(1961年、監督も橋本自身)の脚本を書くにあたり、創作ノートに記した文章の主要部分。
全文は以下。
| 人間は、生まれて、生きて、死んで行く。 その生きていく間が人生である。 |
|
| 人生とはなんだらう。 | |
| 恰もそれは賽の河原の石積みのようなものである。 笑ったり泣いたりしながら、みんな、それぞれ自分の石を積んでいく。 |
|
| ところが、時々、自分達の力ではどうしようもない鬼(災難その他)がやって来て、金棒で無慈悲にこの石を打ち崩す。 | |
| 人間はその度に涙を流す。 | |
| 表面的な涙だけではない。心の中が、いや、身体全体までが涙で充満する。 | |
| そして、嘆き悲しみながらも、また石を積み始める。 |
|
| その涙の底には、その人自身は気がつかないにしても、何かとても強い意志・・・・・・生きていこうとする何ものかが・・・・・・不思議なほどに強い生命力がある。 | |
| もし、地球上のあらゆる生物が死滅したとしても、最後まで生き残るのは、人間ではなかろうか。 | |
| 現実の社会は一見、ひどく複雑である。 | |
| 従って、その中に生きている人間までが複雑に見える。 | |
| しかし、もっと人生を俯瞰的に見れば、いや、一人一人の心の中え素直に入り込んでみれば、案外、人間ほど素朴で、悲しく美しい、そして強いものはないように思える。 | |
| その姿を的確に描き出すことが、「現代の詩」を生み出すことではなからうか。 |
春日太一は、橋本忍の作品についてこう述べる。
| 「 | そうした、「鬼」たちによる容赦ない理不尽に踏みにじられる人々の姿を、橋本はひたすら描いてきた。 |
| なにせ脚本家としてのデビュー作である「羅生門」からして、美しい妻と旅をしていた武士が、盗賊に殺害される話だ。 | |
| また、主だった現代劇を挙げるだけでも・・・。殺人犯として無実の罪を着せられる「真昼の暗黒」。 人の好い理容師が、戦時中に上官の命令で犯した罪のために、戦後の軍事法廷で死刑になる「私は貝になりたい」。 暗い過去を持ち、苦労を重ねた者がようやく幸福を掴みかけたところで、事件捜査により全てを失う「張込み」「ゼロの焦点」「砂の器」。 一方的な逆恨みのために築いてきた栄光を失う「霧の旗」。 自然の猛威の前に人々の営みが全て飲み込まれていく「日本沈没」。 上層部の無謀な命令のために、史上最悪の山岳遭難事故が起きる「八甲田山」。(略) |
|
| ほとんどの作品において橋本は、自分自身ではどうにもならない災厄により悲劇的な状況に陥る人間たちを描いてきたのだ。」 |
橋本自身もまた、たくさんの「鬼」と遭遇する。
| 「 | 晩年に服用していた薬のリストを見ると、糖尿病関係、代謝関係、呼吸器関係、消化器関係、神経・脳関係、精神科関係・・・と多岐にわたり、計十八種類にも及ぶ。 |
| さらに、九〇年代以降だけでも腎臓がん、急性膵炎、膀胱がん、前立腺がん、腸閉塞、脳梗塞、気管支拡張症と、次々と大病を患った。 | |
| 粟粒性結核を患っていたためもともと身体は強くない。 このような状況下にある橋本が、百歳を間近に控えてもなお書き続けたというのは、尋常ならざる執念というより他にない。」 |
「鬼」はこの世に無数にいるらしい。
「8月は 6日 9日 15日」と言う。
「戦争」という名の、人間が造りだした「鬼」が、すぐ近くまでやって来ているような気がする。
石を積もう、石を。
「鬼」が崩しきれぬほどの、たくさんの石を。
2024年07月06日
隠居の控帳 万札うらおもて
7月3日、新しい紙幣が発行された。
一万円札の肖像画は渋沢栄一。

それに伴って、渋沢栄一の経済的業績と道徳的人物像が盛んに讃えられている。
しかし、どんな人物にも多面性があるもので、あまり表に出ない渋沢栄一の一面についても知っておく必要があろう。
一橋大学学生・朝倉希実加氏の「週刊金曜日」誌への寄稿から見てみよう。
韓国が新一万円札の肖像画に反発する理由は、渋沢が明治三十五年(1902)に朝鮮で発行した紙幣に始まる。
一橋大学大学院生・牛木未来氏は、こう言う。
レイバーネットTVより。
一万円札の肖像画は渋沢栄一。

それに伴って、渋沢栄一の経済的業績と道徳的人物像が盛んに讃えられている。
しかし、どんな人物にも多面性があるもので、あまり表に出ない渋沢栄一の一面についても知っておく必要があろう。
一橋大学学生・朝倉希実加氏の「週刊金曜日」誌への寄稿から見てみよう。
| 渋沢が主人公のNHK大河ドラマ「青天を衝け」のハンドブックには、次の記述がある。 | |
| 「昨年、栄一が新紙幣の肖像画のモデルになると発表されるや、韓国国内からは「植民地支配の被害国への配慮にかけている」と批判が出た。無理からぬことだ」。 | |
| 日本が朝鮮を侵略し、渋沢の金融事業や鉄道建設が朝鮮人の土地を奪って、朝鮮人を貧困に追い込み、過酷な労働を強いながら利益を得たという歴史的事実に対する言及である。 | |
| 同書は続いてこう語る。「だが日本にしてみれば、『官尊民卑』な役人暮らしに嫌気がさして財界にその身を投じ、第一国立銀行を立ち上げ、明治日本の財界を背負って立った人物なのだから、肖像画のモデルになってしかるべきなわけだ」。 | |
| つまり、被支配側からはどう見られていようと、日本側から見れば渋沢は偉人であり、彼が英雄視されるのは当然である、という視点である。 |
「一橋大生が迫る渋沢栄一と朝鮮侵略」(週刊金曜日2021.12.10)
韓国が新一万円札の肖像画に反発する理由は、渋沢が明治三十五年(1902)に朝鮮で発行した紙幣に始まる。
一橋大学大学院生・牛木未来氏は、こう言う。
| 「株式會社第一銀行」「壹圓」の文字の隣に威圧的な雰囲気を放つ男性の肖像。渋沢栄一が紙幣の「顔」となるのは、2024年が最初ではない。 | |
| 渋沢を擁した写真の紙幣は、渋沢が設立した第一銀行(日本最初の銀行・第一国立銀行の後身)のものである。1902年から朝鮮半島で流通した。第一銀行が朝鮮に支店を持ったためである。 | |
| 朝鮮人にとってそれは何を意味したのだろうか。(略) |
|
| 日本貨幣の浸透は、朝鮮社会にもともと存在した貨幣の価値を下落・不安定化させ、金融の混乱に乗じて日本商人が投機的な利益を得る一方、朝鮮人商人は大きな損失を被った。(略) |
|
| 第一銀行が貸出において朝鮮人への差別を行った結果、朝鮮人の預金額は貸出額を大幅に超過し、朝鮮人商人は困窮に陥った。(略) | |
| つまり、第一銀行の進出の結果破産した朝鮮人を日本経済に従属させ、朝鮮独自の金融体系を破壊したのである。 | |
| 一方、朝鮮人や外国人(中国商人と思われる)の超過預金は朝鮮に進出した日本企業や商人の資金とされた。 | |
| 彼らは事業の展開に当たり朝鮮人から土地や生産手段を奪い、労働者として過酷な条件で働かせた。(略) |
|
| 以上のような経済侵略を前提として、植民地期には日本による収奪政策が強化された。 | |
| その結果、大部分の朝鮮人は慢性的な貧困状態に陥った。 そして、貧困を背景として、多くの朝鮮人が故郷を離れ日本や中国東北部に渡ることを余儀なくされた。 |
(週刊金曜日2021.12.10)
レイバーネットTVより。
2023年11月18日
隠居の控帳 覚悟?錯誤?妄語
戦うのは下々の皆さんで、俺(麻生)じゃねぇよ・・・ってか?
そう言えば、8年前にこんな記事を書いていた。
◇隠居の控帳 戦争絶滅法案
戦争を始める指導者の特質は、主観的願望を客観的事実にすり替える。(保坂正康)
そう言えば、8年前にこんな記事を書いていた。
◇隠居の控帳 戦争絶滅法案
戦争を始める指導者の特質は、主観的願望を客観的事実にすり替える。(保坂正康)
2023年10月21日
隠居の控帳 おろかもの之碑
建碑のいきさつが、陳野守正氏著「大陸の花嫁」の中に書かれています。
| 「 | 1986年10月、群馬県吾妻郡中之条町に小暮久弥氏(あづま会副会長・当時81歳)を訪ね、「おろかもの之碑」を案内していただいた。 おろかもの之碑は1961年(昭和36年)に建てられたが、そのいきさつはつぎのようである。 |
| 戦争中、大政翼賛会、翼賛壮年団、在郷軍人分会等の責任者だった者は、敗戦後、占領政策により戦争犯罪人として1947年(昭和22年)より一切の公職から追放された。 | |
| それから四年後、「公職追放」を解除された吾妻郡内の該当者全員が一堂に会し「あづま会」を結成した。 | |
| 一同は会の設立以前から戦争に協力した行為を深く反省し二度と過ちは繰り返さないようにと、またおたがいに励まし合う意味で年一度の集まりをもっていた。 | |
| そうしているうち公職追放などいずれ世の中から忘れ去られてしまうだろう。 碑を建てたらどうだろうか、そのほうが集まりやすいし、という話になった。 |
|
| そこであづま会設立十周年に際し「おろかものの実在を後世に伝え再びこの過ちを侵すことなきを願い」(碑文の一節)碑を建てることにした。 世話係として西毛新聞社社長富沢碧山氏がおされた。 |
|
| 碑をつくる段階で、「全員の名前を刻んでおくだけでもなんだから、名称を考えべえじゃないか」との発言があった。 それに応えて萩原進氏(吾妻郡長野原町出身、当時群馬県議会図書室長)が「とにかく前後も知らねえで悪いことに協力したのは馬鹿もんだから・・・馬鹿もんというのはおろかもんということだから、どうだ、おろかものとしては・・・。」といった。 するとみんなが「それがよかんべ、馬鹿もんだったのだから、おろかものとしよう。」と同意し、碑の名称が決まった。 |
|
| このような経過を経て1961年(昭和36年)、会員だけで金を出し合い碑を建てた。 碑の表には「おろかもの之碑」、裏面には碑を建てた趣旨と会員80余名の名前を刻んだ。 |
|
| おろかもの之碑は、戦争に駆り出されて死んだ者は一番気の毒で申し訳ないのだからと、英霊殿(現大国魂神社)の境内に建てた。」 |
しかし現在、碑は「大国魂神社」ではなく、800mほど離れた「林昌寺」の山門左に移されています。
地元の遺族会から、「英霊に対して、おろかものとは何だ!」と強い反発・抗議があったのです。
「あづま会」の人たちは、
| 「 | そうじゃない、勘違いしている。 わしらがおろかもんなんだ。わしらがおろかもんのために、あんたたちの息子さんたちみんなが戦争に駆りたてられて戦争で死んだんだ。 その申し開きのために、反省のために碑を建てることにしたのだから、英霊殿に建てるのが一番いいと思って建てたのだ。」 |
そして、建立の翌年、「おろかもの之碑」は「林昌寺」に移されました。
碑背に刻まれた撰文は、後ろの塀との間が狭くて、うまく撮影することが出来ませんでした。
塀に上ることもできず、あきらめて帰ってきましたが、後日、雑誌「上州風 第8号」に碑文が載っているのを見つけました。
自らを「おろかもの」あるいは「罪人」と称してはいるのですが、文中には気になる箇所もあります。
「日本ノ運命ヲ決スル危機ニ際シ 我々ハ当時ノ職務上 或イハ一方的委嘱状ニヨッテ一律ニ・・・責任者トナッタ」であるとか、「本意ナキ罪人ハ互ニソノ愚直ヲ笑イ合ッタ」という部分です。
そこには、「止むを得なかったんだ」「本意ではなかったんだ」という気持ちがにじみ出ていますが、本当にそうだったのでしょうか。
私はこの碑を、「付和雷同自戒之碑」と呼びたいと思います。
【おろかもの之碑】
2023年06月03日
魂の演説 櫛渕万里と斎藤隆夫
【櫛渕万里 懲罰動議に対する弁明演説】
【斎藤隆夫 反軍演説】
【新憲法とわれらの覚悟】
これは、今から75年前、日本国憲法が公布されて間もなく、23歳の青年が書いた論考の一部である。青年の名は、芦部信喜(1923~1999)。
のちに「戦後日本を代表する」という定冠詞がつく憲法学者である。
| 「 | 血のにじむ苦闘を通じて戦いとられた欧米の民主主義が、新憲法の発布により簡単に実現すると考えたり、「憲法より飯だ」と国民一般がこれに無関心であったならば、いかに国民主権主義を宣言しても、人民の幸福をもたらす政治は到底実現されるはずはなかろう。(略) |
| もちろん新憲法が現代的憲法としてはいくたの不完全さをもつことは否定できない。が、現在われわれ国民としての責務はかかる不完全さをせんさくすることでなく、この憲法を生かすことを真剣に考えることである。 そしてそれはわれわれの「主体的意識の覚醒」の一語につきると私は思う。 (略) |
|
| われわれの思想的動向が、右に左にただ時論の赴くままに無定見に浮動し、何らの節操もない為政者を選出して異とも感じない考え方が依然として改められず、相変わらずの被統治者根性に支配されて主体の意識をとり戻さぬ限り、新憲法の下に再び過去の変改が繰り返されることが決してないとは言えない。(略) | |
| 民主日本が民主主義制度の確立と相まって国民的精神の革命的浄化を必須とする所以はこの点にあるのである。 だから生活の窮迫に藉口して深い自覚を以て民主主義的信条を陶冶するの努力をもなさず「われらは治められるもの」との考えを固執し法に無関心である限り、愚劣な為政者が横行して「現在の日本人の頭では未だ何を作ってもだめである」(尾崎行雄-憲法発布に際して)という悲しむべき状態は改められないであろう。(略) |
|
| 誠に平和日本の建設の成否したがって新憲法の成否は、一にかかって国民の資質にある。」 |
(「世界」2022年5月号より)
2022年06月25日
隠居の控帳 ひたひたと・・・
6月17日~30日 「シネマテークたかさき」にて上映
原作:ジェームズ・クラベル
翻訳:青島幸男
「The Children's Story...
(but not just for children)」
翻訳:青島幸男
「The Children's Story...
(but not just for children)」
2022年06月11日
隠居の控帳 じわじわと・・・
| 1947 | 日本国憲法制定(国民主権、平和主義、戦力不保持) |
| 1950 | 朝鮮戦争勃発(在日米軍出動) |
| 1950 | 警察予備隊創設(日本再軍備開始) |
| 1954 | 自衛隊法制定(陸海空自衛隊発足) |
| 1967 | 武器輸出三原則制定 |
| 1976 | 防衛費GDPの1%に |
| 1991 | 自衛隊初の海外派遣 |
| 1992 | PKO協力法制定(平和維持活動のための自衛隊海外派遣容認) |
| 1999 | 国旗国歌法成立 |
| 1999 | 通信傍受法(盗聴法)制定 |
| 2003 | 武力攻撃事態法制定(私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物資の輸送や戦傷者治療等のための役務強制等可能に) |
| 2004 | 絵本「戦争のつくりかた」出版 |
| 2005 | 自衛隊法改訂(ミサイル迎撃命令可能に) |
| 2006 | 教育基本法改訂(国を愛する態度、道徳心、公共の精神、伝統の尊重を強調) |
| 2009 | 民主党政権誕生 |
| 2012 | 自民党政権復活 |
| 2012 | 自民党改憲草案作成(集団的自衛権の行使を容認。天皇を「日本国の元首」と位置づけ、日の丸や君が代の尊重を義務づけ。) |
| 2013 | 特定秘密保護法制定(国が特定秘密だと指定したら、その情報を知ろうとするだけで罰せられる。) |
| 2014 | 憲法第9条解釈変更閣議決定(集団的自衛権を容認) |
| 2015 | 安保法成立(集団的自衛権を法制化) |
| 2015 | 道徳の教科化(個人より公共を重んじ愛国心を醸成する教育、内心の評価) |
| 2017 | 教育勅語政府見解(教材として教育勅語を使用してもよい) |
| 2017 | テロ等準備罪(共謀罪)法成立(国民の思想・内心・対話などを処罰の対象に) |
| 2018 | 司法取引制度施行(密告の誘導) |
| 2020 | 日本学術会議会員任命拒否(学問への政治介入) |
| 2021 | 歴史教科書記述表現閣議決定(「従軍慰安婦」や「強制連行」の表現は不適切と) |
| 2021 | 重要土地利用法制定(個人情報が国に収集され、思想信条や表現の自由、財産権を侵害する恐れ) |
| 2022 | 経済安保法制定(企業の経済活動や学術研究活動に国が介入し、秘密の強要や軍事化を招く恐れ) |
| 20?? | 敵基地攻撃能力保持閣議決定?(専守防衛から先制攻撃へ) |
| 20?? | 憲法に自衛隊を明記?(法律や政令で軍隊としての活動が可能になる) |
| 20?? | 憲法に緊急事態条項制定?(政府への全権委任により、国会を開かずにどんな法律でも制定が可能になる) |
アクセスカウンタ
ブログ内検索
最近の記事
室田街道 無いもの散歩(6) (5/17)
室田街道 無いもの散歩(5) (5/3)
室田街道 無いもの散歩(4) (4/19)
室田街道 無いもの散歩(3) (4/5)
室田街道 無いもの散歩(2) (3/22)
室田街道 無いもの散歩(1) (3/8)
もう一つの「左道通行」 (2/22)
碩 (2/8)
あのさぁ、みんなさぁ・・・ (2/1)
句碑を探して姨捨へ(2) (1/18)
過去記事
最近のコメント
迷道院高崎 / あった!お城だ!
磯城津彦玉手看尊 / あった!お城だ!
迷道院高崎 / 史跡看板散歩-217 下室田の・・・
夏目吉春 / 史跡看板散歩-217 下室田の・・・
迷道院高崎 / 室田街道 無いもの散歩(2)
清水一也 / 室田街道 無いもの散歩(2)
迷道院高崎 / 史跡看板散歩-162 冷水の小祝様
ふ〜みんママ / 史跡看板散歩-162 冷水の小祝様
迷道院高崎 / 室田街道 無いもの散歩(1)
稲荷横丁そだち / 室田街道 無いもの散歩(1)
カテゴリ
◆高崎探訪 (103)
└
高崎町なか (102)
└
遠構え散歩 (6)
└
高崎唱歌 (56)
└
高崎市名所旧跡案内板 (275)
└
観音山遠足 (75)
└
例幣使街道 (19)
└
観音山 (99)
└
倉賀野 (53)
└
新町(しんまち) (19)
└
吉井町 (16)
└
高崎の絹遺跡 (5)
└
田村隧道 (5)
└
藤森稲荷 (5)
└
高崎五万石騒動 (20)
└
高崎藩銚子領 (16)
└
小栗上野介 (11)
└
鎌倉街道 (42)
└
…続・鎌倉街道 (26)
└
三国街道 (47)
└
…切干塚(首塚) (6)
└
…春の夜嵐 (7)
└
中山道 (15)
└
米街道 (4)
└
実政街道 (6)
└
...続・実政街道 (12)
◆高崎雑感 (146)
└
高崎茶話会 (3)
└
思い出 (9)
└
願い (14)
└
音楽センター (3)
└
柳家紫文 (33)
└
米百俵コンサート (23)
◆出・たかさき (67)
◆上州弁手ぬぐい (19)
◆世事雑感 (30)
◆私事雑感 (23)
◆隠居の控帳 (86)
└
沈思黙考 (70)
└
二宮金治郎 (11)
Information
読者登録
プロフィール

迷道院高崎
リンクはご自由にどうぞ。
(確認メールは不要です。)
よろしければ、下のバナーをご利用ください。
(確認メールは不要です。)
よろしければ、下のバナーをご利用ください。

QRコード





































