 最後に「風」で歌ったのは、35年ほど前だったと思う。
最後に「風」で歌ったのは、35年ほど前だったと思う。夫婦喧嘩をして飛び出したものの行き場もなく、学生の頃に通い詰めた「風」で歌を歌って時間を潰していた。
ところが女房の勘というのはすごいもので、ここをぴたりと探し当てられてしまった。
歌を歌って私の怒りも収まっていたので、無事休戦(敗戦かな?)できた。
今日まで夫婦でいられるのは、もしかしたら「風」のおかげかも知れない。
郊外に引っ越し、すっかりご無沙汰になってしまったある日。
前を通りかかって懐かしく「風」の看板を見上げたが、店を開いている様子はなかった。
その時は、1階の薬屋さん「マツヤス薬局」がまだやっていたので、ご主人にお話を聞くことができた。
ご主人から聞いて初めて知ったのだが、「風」を開いていたのは「マツヤス薬局」の奥様だったのだ。
お身体を壊されて、やむなく「風」を閉めることになったのだが、「看板は残しておいて。」と言われているので、ということだった。
またいつか「風」を再開するつもりなのだな、再開されたら絶対に来ようと思っていたのだが、ついに「マツヤス薬局」のシャッターも降ろされてしまった。
「風」には、カウンター席が6つぐらい、4人がけくらいのテーブル席がやはり6つぐらいあったような記憶がある。
いつも満席に近く、ガラガラだった記憶はない。
伴奏はエレクトーンだった。その伴奏に合わせてリーダーが歌い、客が一緒に歌うのだ。
1曲歌い終わると、客席から「(歌集)何集の何番!」とリクエストが出る。
客は一斉にそのページを開いて、伴奏が始まるのを待つ。
今のカラオケのように、一人が歌い、他の人はろくに聞きもせずに曲探しという冷たさはない。
みんなが一緒だった。
みんなと歌いながら、知らなかった歌をずいぶん覚えた。
特に、山の歌、ロシア民謡、労働歌はよくリクエストされていた。
ママ(マツヤス薬局の奥様)は、いつも笑顔でカウンターの中にいた。
初めて「風」に入ったのは中学3年生の時だった。
当時は、中学生が喫茶店に入るのは禁止されていたかも知れない。
だが、昼飯のパンを買う金を2日我慢して貯め、「風」に通っていた。
初めての日は金がなくて歌集が買えなかった。(1冊100円ぐらいだったかなぁ?覚えてない。)
ママは笑顔で店の歌集を貸してくれた。
ある日こんなことがあった。
見るからにその筋らしいお兄さんと、その手下らしい人が店に入ってきてカウンター席に座った。
横目でチラチラ見ていると、お兄さんも「場違いなところに来ちゃったなぁ。」という顔をして、黙ってコーヒーを飲んでいた。
すると、ママが少しも臆することなくいつもの笑顔で、
「ほら、歌いなさいよ!」とお兄さんに歌集を手渡すと、照れたような顔で小さく開けた口で一緒に歌い始めた。
心の中で「すげー!ママ!」と感心することしきりだった。
あの頃の「同胞感」って、今、必要なんじゃないかなー。



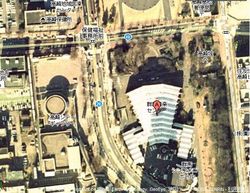






 高崎には
高崎には












 ここ何年か、初詣は上中居町の
ここ何年か、初詣は上中居町の
 この神社は、
この神社は、


 ただ、成田町には
ただ、成田町には
















 明治37年、製造煙草専売法が議会で可決されると、いち早く、八島町に
明治37年、製造煙草専売法が議会で可決されると、いち早く、八島町に


































