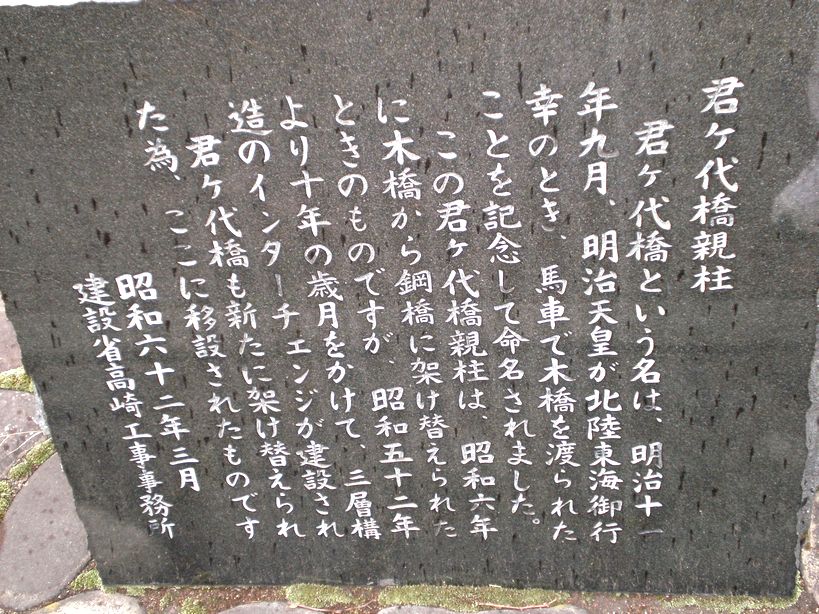矢中町に、「ゴロゴロ山」と言うのがあると聞いていて、ずーっと気になっていた。
今日は朝から曇り空だが、風がないのに勇気づけられ、散歩がてら探してみることにした。
あるとすればこの辺だろうと見当をつけ、道を1本通り抜けたが見つからない。
1本南の道をもう一度通り抜けたが、見つからない。
そのまた、もう1本南の道は、車の通りの多い道で、そこは何度も通ったことがある。
まさか、この道沿いにあるはずは・・・、と思っていたら・・・あった!
なーんだ、ここかー。
人間というのは、「見ようと思わなければ、見ても見えない」ということがよく分かった。
 「山」とは言うものの、ちょっと高めの盛り土という感じである。
「山」とは言うものの、ちょっと高めの盛り土という感じである。
ただ、そこに生えている木は迫力がある。
北京五輪の100mで金メダルを獲った、ジャマイカのボルト選手のような格好をしている。
榎(えのき)とも椋(むく)とも言われるが、正解は何だろう?
 木の根元に、石の祠がある。
木の根元に、石の祠がある。
これは、昔、歯の病で死んだ巡礼の墓だと言われている。
言い伝えでは、歯が痛む時に、土を一升この山に持ってきて撒くと、痛みが治まるという。
言い伝えといえば、昔この辺では、よくキツネに化かされて、ふんどし一丁にされてしまうという話があったらしい。
その実は、倉賀野の宿場へ遊びに行って、博打や女郎に金を使って無一文になり、身ぐるみ剥がされて家に帰るはめになった、村の男の言い訳だったようだ。
そんな言い訳が通った昔は、いいなぁー。
 ところで、「ゴロゴロ山」という名前の由来だが、昔、ここの木に雷が落ちたことがあったそうで、その時の音から「ゴロゴロ山」と呼んだのだそうだ。
ところで、「ゴロゴロ山」という名前の由来だが、昔、ここの木に雷が落ちたことがあったそうで、その時の音から「ゴロゴロ山」と呼んだのだそうだ。
確かに、この木の幹には大きな洞(うろ)がある。
その時の裂け目の跡であろう。
それにしても、こんなにひどい傷を負いながら、今日の大きさまでよくまぁ頑張って生き続けたものだ。
歯の痛みを取るという話は、もしかしたら、この傷跡が虫歯の穴のように見えたからではないかと思った。
今日は朝から曇り空だが、風がないのに勇気づけられ、散歩がてら探してみることにした。
あるとすればこの辺だろうと見当をつけ、道を1本通り抜けたが見つからない。
1本南の道をもう一度通り抜けたが、見つからない。
そのまた、もう1本南の道は、車の通りの多い道で、そこは何度も通ったことがある。
まさか、この道沿いにあるはずは・・・、と思っていたら・・・あった!
なーんだ、ここかー。
人間というのは、「見ようと思わなければ、見ても見えない」ということがよく分かった。
 「山」とは言うものの、ちょっと高めの盛り土という感じである。
「山」とは言うものの、ちょっと高めの盛り土という感じである。ただ、そこに生えている木は迫力がある。
北京五輪の100mで金メダルを獲った、ジャマイカのボルト選手のような格好をしている。
榎(えのき)とも椋(むく)とも言われるが、正解は何だろう?
 木の根元に、石の祠がある。
木の根元に、石の祠がある。これは、昔、歯の病で死んだ巡礼の墓だと言われている。
言い伝えでは、歯が痛む時に、土を一升この山に持ってきて撒くと、痛みが治まるという。
言い伝えといえば、昔この辺では、よくキツネに化かされて、ふんどし一丁にされてしまうという話があったらしい。
その実は、倉賀野の宿場へ遊びに行って、博打や女郎に金を使って無一文になり、身ぐるみ剥がされて家に帰るはめになった、村の男の言い訳だったようだ。
そんな言い訳が通った昔は、いいなぁー。
 ところで、「ゴロゴロ山」という名前の由来だが、昔、ここの木に雷が落ちたことがあったそうで、その時の音から「ゴロゴロ山」と呼んだのだそうだ。
ところで、「ゴロゴロ山」という名前の由来だが、昔、ここの木に雷が落ちたことがあったそうで、その時の音から「ゴロゴロ山」と呼んだのだそうだ。確かに、この木の幹には大きな洞(うろ)がある。
その時の裂け目の跡であろう。
それにしても、こんなにひどい傷を負いながら、今日の大きさまでよくまぁ頑張って生き続けたものだ。
歯の痛みを取るという話は、もしかしたら、この傷跡が虫歯の穴のように見えたからではないかと思った。
傷負いて 故に知りうる 人の傷 <迷道院>
「ゴロゴロ山」の石仏
(参考図書:「高崎漫歩」)
【ゴロゴロ山】











 良い方との出会いにより少し勇気が湧いたので、もう一度
良い方との出会いにより少し勇気が湧いたので、もう一度



































 上毛かるたでは
上毛かるたでは