 石原町の「小祝(おぼり)神社」は、安産の神様として知られている。
石原町の「小祝(おぼり)神社」は、安産の神様として知られている。妊娠した女性は、戌の日にこの神社へお参りして腹帯を借り、無事出産したら新しい腹帯を添えて返す習わしがある。
私と妻も、そうやって二人の丈夫な子供を授かった。
「小祝神社」の創建がいつかは定かでないようだが、平安時代の延長5年(927年)の延喜式神名帳に記載されているというから、少なくとも千年以上は経っている由緒ある神社である。
その神名帳によると、上野(こうづけ)十二社の第七社に位している格の高い神社だ。
そして、祭神は「少彦名命」(すくなひこなのみこと)である。
このことが、古代のロマン溢れる話を空想させる。
 日本神話で、「大国主命」(おおくにぬしのみこと)が国造りをしたことは有名な話である。
日本神話で、「大国主命」(おおくにぬしのみこと)が国造りをしたことは有名な話である。その時、半島からやってきて協力したのが「少彦名命」だと言われている。
農耕の神様ということから、万物を産む→安産の神様となったのであろう。
「少彦名命」はとても小さな神様で、ガガイモの実の舟に乗ってやってきたという。
そこから、一寸法師のモデルとも言われている。
「大国主命」と国造りに励んでいた「少彦名命」だが、ちょっとした意見の相違が生じたようで、ある日、粟の茎に登って常世の国(とこよのくに)に弾き飛んで行ったそうである。
 アイヌ神話には、コロボックルという小さな神様が登場するが、これが実は「少彦名命」ではないかという説もある。
アイヌ神話には、コロボックルという小さな神様が登場するが、これが実は「少彦名命」ではないかという説もある。佐藤さとる氏著「だれも知らない小さな国」は、現代にコロボックル達が登場し、少年と一緒に住み処の小山を守るというファンタジー小説である。
小説の中では、この小人たちを「小法師(こぼし)さま」と呼んでいる。
何となく「小祝(おぼり)さま」に似ている。
さて、ここで思い出してほしいことがある。
観音山の清水寺は、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の途中で、この地に京都の観音様を勧請して開基したと言われていることだ。
古代の群馬県は、「毛の国」(けのくに)と呼ばれていたことから、体毛の濃い民族が住んでいたという説がある。
体毛が濃いのはアイヌ民族の特徴でもあるので、古代の群馬県人はアイヌ民族だったのではないかという。
とすれば高崎にアイヌ民族が住んでいたとしても不思議はない。
その民族の信仰する神様が「小祝神社」だったのではないだろうか。
いや、もしかするとコロボックルそのものが、この地に住んでいたのかも知れない。
ある日、その民族が田村麻呂によって土地を追われ、「常世の国」(北海道)まで移動していったとは考えられないだろうか。
そう、
コロボックルは高崎にいたのである!
観音山の山麓は
コロボックル達の住む
「小人の国」だったのだ!
【小祝神社】


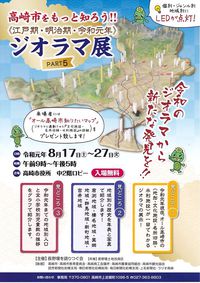

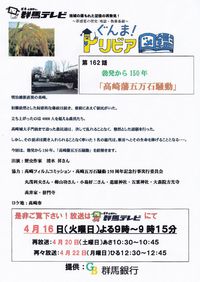

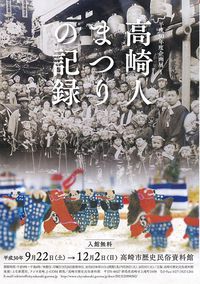
 at 2009年02月17日 20:48
at 2009年02月17日 20:48





