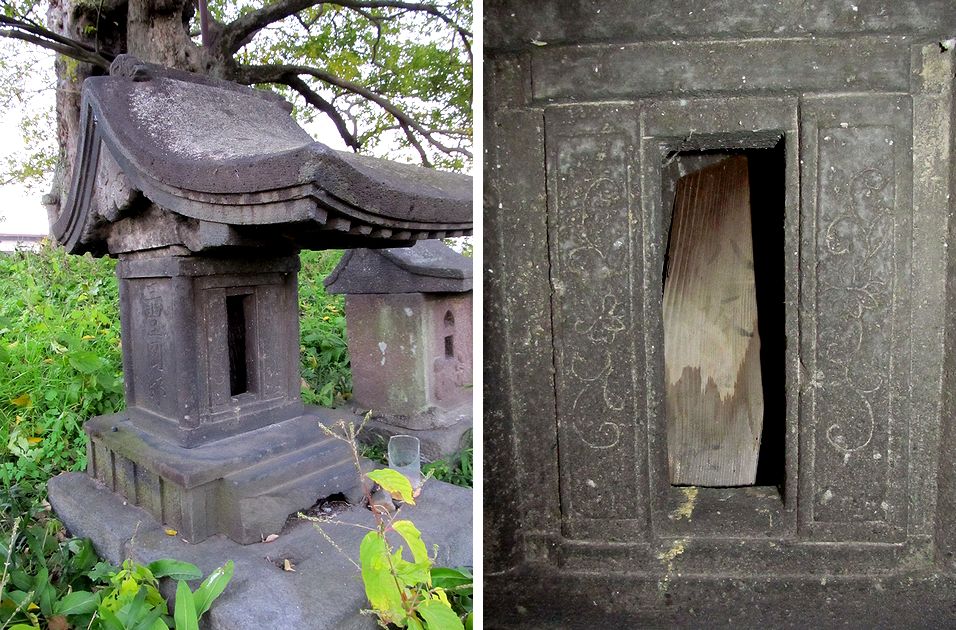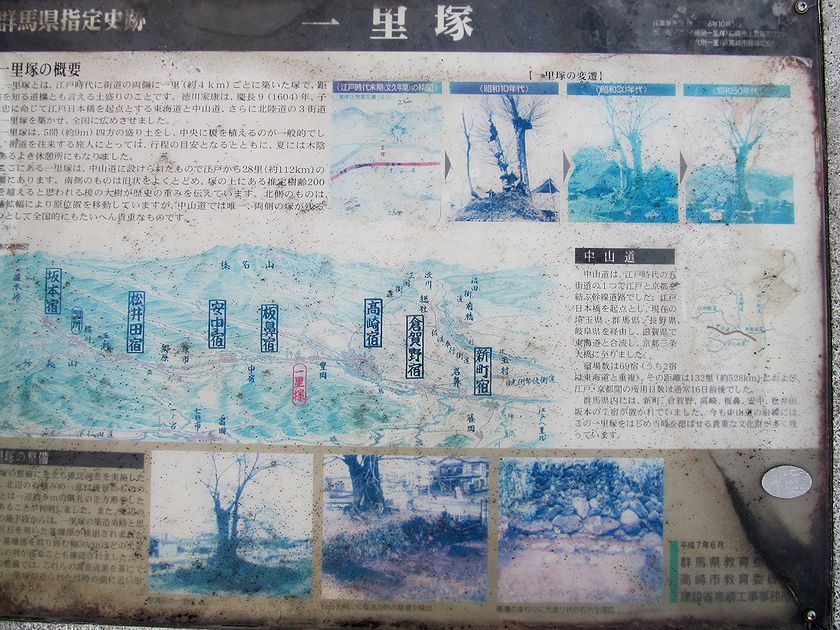明治三十七年(1904)袋井学術講話会に於ける、内村鑑三の講演大要より抜粋。
| 「 | 予(内村鑑三)は嘗(かつ)て『日本及日本人』(後に『代表的日本人』と変更)なる一書を英文にて著し之を世に示したり。 |
| 録する処、西郷隆盛、日蓮上人、上杉鷹山公等なりしが、之を読んで英米人の尤も(最も)驚嘆せしは二宮尊徳先生なりしと云ふ。 | |
| 彼らが異教国と称するこの国に、かくの如き高潔偉大の聖人あらんとは、彼らの意外とせしところなりしと見ゆ。 | |
| 若(も)し欧米人が詳(つまび)らかに先生の性行閲歴を知りえたらんには、恐らく先生を以って世界における最高最大の人物に数ふるならん。(略) |
|
| 近年日本に産出せられたる書物の中にて尤も大なる感化力あるものは、二宮先生の報徳記に若(し)くものなし。予が小児らに先(ま)づ読ましめたきものは即ちこの書なり。(略) | |
| 何故にこの書がかく偉大なる感化力を有するや、他なし、之れ真正の経済なるものは道徳の基礎に立たざる可からざることを、先生の事業生涯を以って説明したるものなればなり。 | |
| 即ち身を以ってこの問題の解決を為したるなり。先生は経済と道徳の間に橋をかけたり。先生の一生は経済道徳問題の福音なり。この意味において報徳記は一部のクラッシック(古典)也。経書なり。 |
|
| 抑(そもそ)も現今経済を論ずるものは大抵倫理道徳と関係もなきものと為すものの如し。(略) | |
| アダムスミスの『富国論』は著名なり。邦人皆之を読みて経済学上の大著となす。然れども彼は之をその倫理学の一篇として書きたるものなり。 | |
| 然るに現今英米の学者輩、経済学を以って単に利慾の学問とせり。(略) | |
| 先生は否(しか)らず。道徳は原因にて、経済は結果なりと断じたり。至誠勤勉正直にして初めて経済の成立するものなりとせり。(略) | |
| 今日の経済学者は先づ算盤を手にす。先生は先づ至誠の有無を質(ただ)す。吾人、先生に学ぶところなきか。 |
|
| 今や不景気の声高し。この救済策を以って先生に問はば先生必ず云はん。先づ之を救わざる可からず。不景気の救済は不道徳の救済ならざる可からずと。 | |
| 今時の人、ややもすれば挽回策を以って農工銀行や商業銀行の設立によると為す。然れども人心腐敗すれば斯くの如きものは却って之れ不景気の前駆となり、破産の機関となり了(おう)せん。(略) | |
| 畢竟(ひっきょう:つまる処)、経済の本(もと)は金にあらずして人の心にあるなり。 | |
| 此の点に於いて、先生の経済論は実に敬服の外なきなり。今の経済学者は、只之を以って金銭利慾の問題となして、人の意志に関する無形の倫理道徳の問題なるを知らず、真に憐れむべきにあらずや。」 |
(岩波書店「内村鑑三選集4 世界の中の日本」)