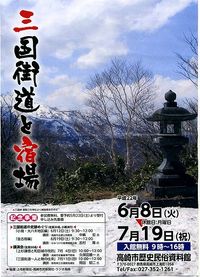「常仙寺」の本堂の裏にも、びっくりするようなものがあります。
「常仙寺」の本堂の裏にも、びっくりするようなものがあります。
「往生楽土」と書かれた仏塔には、お釈迦様が鎮座していらっしゃいます。
右奥のお堂は、立派な六角形校倉(あぜくら)造りの開山堂です。
 榛名の山並みをバックに、6~7m位あるでしょうか、見上げるような十一面観音像が建っています。
榛名の山並みをバックに、6~7m位あるでしょうか、見上げるような十一面観音像が建っています。
「高岡大仏」で有名な、富山県高岡市で鋳造されたものだそうですが、実に美しいお顔とお姿をしています。
観音山の清水寺にも、かつて、鋳銅の「露天聖観世音立像」があったといいますが、今、残っていたらなあと思います。
 観音像前にも「摩尼車(まにぐるま)」がありますが、ちょっと変わっています。
観音像前にも「摩尼車(まにぐるま)」がありますが、ちょっと変わっています。車には文字でなく、絵が描かれています。(写真をクリックしてみてください。)
これは、「絵心経(えしんぎょう)」というもので、字の読めない人でも「般若心経」を唱えられるようにと、考案されたそうです。
元禄(1688~1703)の頃、南部地方(岩手)の寺社取締役人・善八という人の発案と言われますが、ちょっとだけ見てみましょうか。

摩訶(まか)・・・釜が逆さまで「まか」です。

般若(はんにゃ)・・・説明不要。

波羅(はら)・・・「腹」です。

蜜(み)・・・「箕(み)」ですが、最近あまり見ないかな?

多(た)・・・田んぼですね。

心経(しんぎょう)・・・神鏡(しんきょう)、神棚にある鏡です。
ということで、続けると、
「摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみたしんぎょう)」
となる訳です。

仏教詩人・坂村真民の「念ずれば花開く」の詩碑もありました。
飯塚の「長泉寺」にもありましたが、私の大好きな詩です。
「常仙寺」は、良い檀徒さんに恵まれたのでしょう。
素晴らしいもの、立派なものが沢山奉納・寄進されています。

でも、私が一番感銘を受けたのは、この灯籠でした。
奉納者は、「匿名の一檀徒(女性)」とあります。
さらに、「平成十三年一月より毎月浄財送金」とあります。
毎月浄財を送金する、匿名女性もさることながら、その浄財をこのような形で残す「常仙寺」さんの心にも、いたく感銘を受けました。
 「常仙寺」に行くなら、風の日をお勧めします。
「常仙寺」に行くなら、風の日をお勧めします。本堂や、灯籠に吊り下げられた風鐸が風に揺れ、爽やかな音を響かせる度に、我が身の煩悩がひとつづつ消えていくような、そんな気分を味わえると思います。 合掌
【常仙寺】