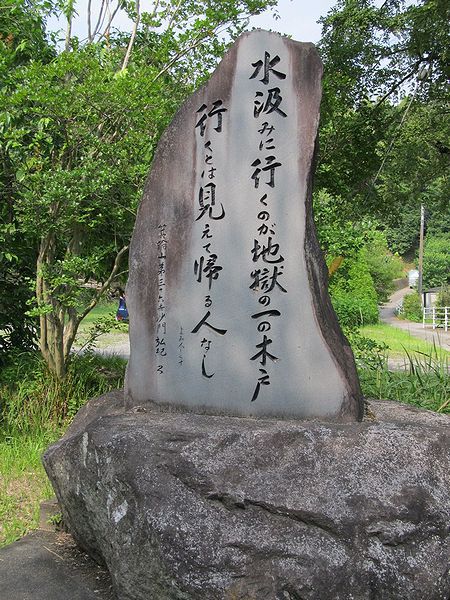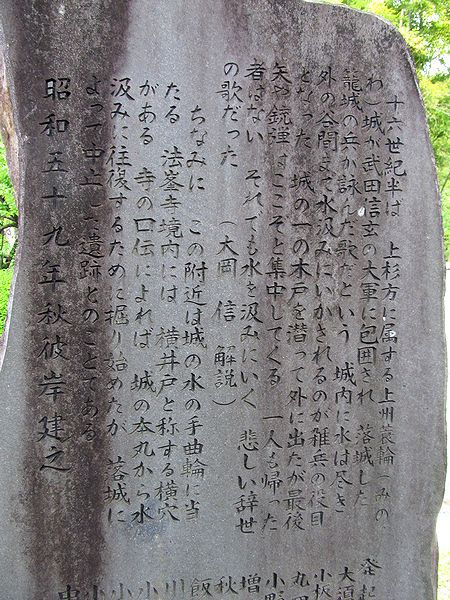「箕輪小学校」へ来たついでに、すぐ裏の「法峰寺」(ほうぼうじ)へ行ってみました。
校庭とグランドの間を参道が抜けています。
長い参道で、入口から240mほど入ってようやく参道らしくなります。
こんな石碑が建っています。
「水汲みに 行くのが地獄の 一の木戸
行くとは見えて 帰る人なし」
どういう意味なんでしょうか。
ちゃんと碑背に刻んでありました。
ほー、なるほど。
「箕輪城」の案内看板に、現在地が記されています。
現在地の下んところは、かつて「椿名沼」(つばきなぬま)という泥湿地帯で、敵がここから侵入するのは困難だったそうです。
その「椿名沼」の跡は、いま「蛍峰園」(けいほうえん)という蛍の名所になっています。




その先の石段を上ると、「法峰寺」です。
貞観六年(864)慈覚大師の開基、ご本尊は阿弥陀如来だそうです。
横から見ると、すぐ後ろに「箕輪城」の城山が迫っているのがよく分かります。
「箕郷町誌」に、「法峰寺」の由来がこう書かれています。
「箕輪城」築城の際に立ち退かせた後、城の「水の手曲輪(郭)」として防御の要としたようです。
本堂脇の「夏椿」がきれいでした。
本堂左の小さな社に・・・、
お不動様がいらっしゃいました。
隣にもうひとつお堂があって・・・、
中には結構な彫刻のお宮が安置されています。
ご住職にお尋ねしたら、山王様だそうです。
神仏混淆時代の名残なんでしょうね。
その「山王堂」の前の石段を上った所に、もうひとつ大きなお堂があります。
聖観音を祀った「観音堂」で、旧群馬郡三十二番札所になっています。
本堂裏に、湧水を利用した小さな池があります。
「箕輪城」があった時はもっと大きかったようで、上方に水櫓を建て、つるべで水を城に揚げたといいます。(箕郷町誌)
その池の上の崖に、ぽっかり開いた穴があります。
前出の「水汲みに・・・」碑の碑背に、こんな文言があったのを思い出してください。
これが、その横穴なんだそうです。
うーん、面白い!
校庭とグランドの間を参道が抜けています。
長い参道で、入口から240mほど入ってようやく参道らしくなります。
こんな石碑が建っています。
「水汲みに 行くのが地獄の 一の木戸
行くとは見えて 帰る人なし」
どういう意味なんでしょうか。
ちゃんと碑背に刻んでありました。
ほー、なるほど。
「箕輪城」の案内看板に、現在地が記されています。
現在地の下んところは、かつて「椿名沼」(つばきなぬま)という泥湿地帯で、敵がここから侵入するのは困難だったそうです。
その「椿名沼」の跡は、いま「蛍峰園」(けいほうえん)という蛍の名所になっています。




その先の石段を上ると、「法峰寺」です。
貞観六年(864)慈覚大師の開基、ご本尊は阿弥陀如来だそうです。
横から見ると、すぐ後ろに「箕輪城」の城山が迫っているのがよく分かります。
「箕郷町誌」に、「法峰寺」の由来がこう書かれています。
| 「 | 天安年中に天台座主慈覚大師の開基にかかり、戦国の武将長野伊予守信業初めて箕輪城を築く際、寺の境内地が城郭内に亘る故に、交渉の結果、東方十数町に替地を出して寺の移転を行った。 |
| 慶長三年高崎城に移封した際、旧縁の地なるを以て現在地に復した。」 |
「箕輪城」築城の際に立ち退かせた後、城の「水の手曲輪(郭)」として防御の要としたようです。
| 「 | この廓は南側の土居を構えた弦に当る部分の長さ80mの半円形である。 奥行30m、土居の外側は三段の小崖の外に、当時は椿名沼の泥湿地が迫り近接を許さなかった。 |
| 全く絶好の水の手だったのである。」 |
(箕郷町誌)
本堂脇の「夏椿」がきれいでした。
本堂左の小さな社に・・・、
お不動様がいらっしゃいました。
隣にもうひとつお堂があって・・・、
中には結構な彫刻のお宮が安置されています。
ご住職にお尋ねしたら、山王様だそうです。
神仏混淆時代の名残なんでしょうね。
その「山王堂」の前の石段を上った所に、もうひとつ大きなお堂があります。
聖観音を祀った「観音堂」で、旧群馬郡三十二番札所になっています。
本堂裏に、湧水を利用した小さな池があります。
「箕輪城」があった時はもっと大きかったようで、上方に水櫓を建て、つるべで水を城に揚げたといいます。(箕郷町誌)
その池の上の崖に、ぽっかり開いた穴があります。
前出の「水汲みに・・・」碑の碑背に、こんな文言があったのを思い出してください。
| 「 | 法峰寺境内には、横井戸と称する横穴がある。 |
| 寺の口伝によれば、城の本丸から水汲みに往復するために掘り始めたが、落城によって中止した遺跡とのことである。」 |
これが、その横穴なんだそうです。
うーん、面白い!
【法峰寺】