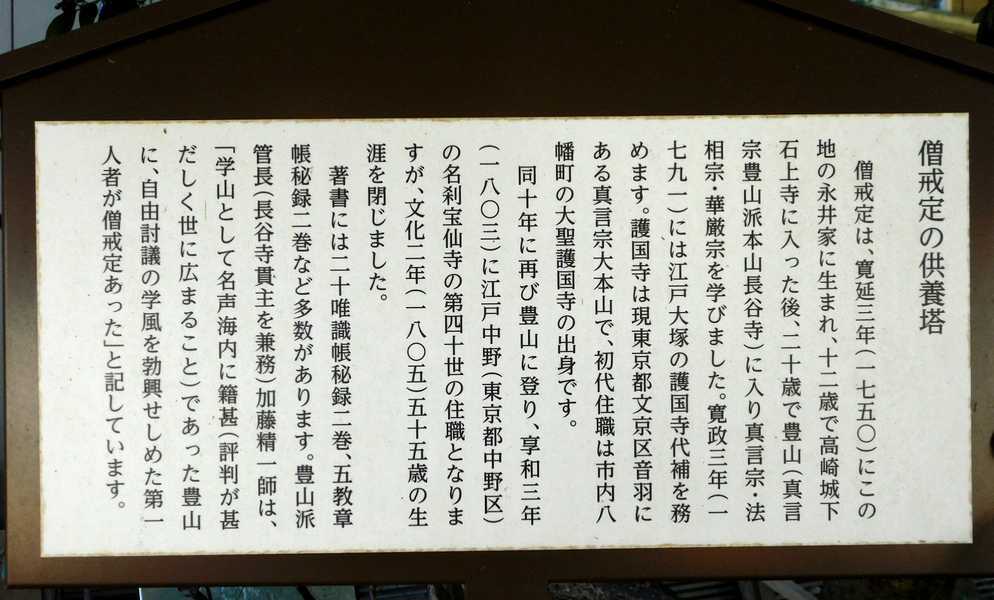ようやく倉渕町へ入りました。
国道406号、「落合」バス停の先を北へ入ります。
入るとすぐ、左側に史跡看板が建っています。
「僧戒定」と書かれていますが、「僧・戒定」とした方が分かりやすいでしょう。
「僧侶の戒丈さん」ということです。
「戒定」は「かいじょう」と読むようです。(倉渕村のあゆみ)
戒定さんについては、看板に書かれていること以上の情報は見つかりませんでした。
強いて言えば、「上野人物志」に少し細かいことが書かれているくらいです。
看板の後ろの塚上に、塔が建っています。
高崎市のHPでは、この塔を「僧戒定の供養塔」としているのですが、そうなのかなぁ?
基台には「明和五戊子年七月日 上野國群馬郡下三倉村」とあり、とくに戒定さんの名は刻まれていません。
明和五年(1768)といえば戒定さんは十九歳、豊山(ぶざん)に入る前年の建立です。
生存中に「供養塔」を建立することはないでしょう。
塔身には、こう刻まれています。
「奉納西國坂東秩父」「日本」「回國」「供養?」。
西国33ヵ所、坂東33ヵ所、秩父34ヵ所、計百ヵ所の観音霊場を回ったことを記念する「回国供養塔」だと思います。
もしかすると、戒定さんが回ったということなのかも知れませんが。
その塔の左隣に、もう一基、ひょろっとした石碑が建っています。
碑面には「武州中野宝仙寺四十世之住 傳燈大阿闍梨法印定慧位 文化二乙丑年正月廿三日」と刻まれています。
「定慧」は「定惠」で、「上野国人物志」にあった、戒定さんの仮の名です。
横面には「髙嵜石上寺辨快御弟子戒定房五十六才」と刻まれています。
「辨快」は、戒定さんを得度させた石上寺の和尚さんです。
碑背に、石碑の建立年と建立者が刻まれています。
「文化八辛未三月立之」、「永井粂右衛門吉長作」。
戒定さん入寂後に永井家で建てたものです。
「僧・戒定の供養塔」と言うなら、こちらの方でしょう。
ところで、このすぐ近くに、有名な「落合の双体道祖神」があります。
真っ昼間から、まぁ、何と大胆な・・・。
どうしてこんなことになったのか、いつか取り調べをしてみたいものです。
国道406号、「落合」バス停の先を北へ入ります。
入るとすぐ、左側に史跡看板が建っています。
「僧戒定」と書かれていますが、「僧・戒定」とした方が分かりやすいでしょう。
「僧侶の戒丈さん」ということです。
「戒定」は「かいじょう」と読むようです。(倉渕村のあゆみ)
戒定さんについては、看板に書かれていること以上の情報は見つかりませんでした。
強いて言えば、「上野人物志」に少し細かいことが書かれているくらいです。
| 「 | 戒定假の名は定惠、金猊園と號す、 |
| 上野國群馬郡三野倉(三ノ倉)の人、俗姓は永井氏、父の名は逾樹、母は土屋氏の出なり、」 |
看板の後ろの塚上に、塔が建っています。
高崎市のHPでは、この塔を「僧戒定の供養塔」としているのですが、そうなのかなぁ?
基台には「明和五戊子年七月日 上野國群馬郡下三倉村」とあり、とくに戒定さんの名は刻まれていません。
明和五年(1768)といえば戒定さんは十九歳、豊山(ぶざん)に入る前年の建立です。
生存中に「供養塔」を建立することはないでしょう。
塔身には、こう刻まれています。
「奉納西國坂東秩父」「日本」「回國」「供養?」。
西国33ヵ所、坂東33ヵ所、秩父34ヵ所、計百ヵ所の観音霊場を回ったことを記念する「回国供養塔」だと思います。
もしかすると、戒定さんが回ったということなのかも知れませんが。
その塔の左隣に、もう一基、ひょろっとした石碑が建っています。
碑面には「武州中野宝仙寺四十世之住 傳燈大阿闍梨法印定慧位 文化二乙丑年正月廿三日」と刻まれています。
「定慧」は「定惠」で、「上野国人物志」にあった、戒定さんの仮の名です。
横面には「髙嵜石上寺辨快御弟子戒定房五十六才」と刻まれています。
「辨快」は、戒定さんを得度させた石上寺の和尚さんです。
碑背に、石碑の建立年と建立者が刻まれています。
「文化八辛未三月立之」、「永井粂右衛門吉長作」。
戒定さん入寂後に永井家で建てたものです。
「僧・戒定の供養塔」と言うなら、こちらの方でしょう。
ところで、このすぐ近くに、有名な「落合の双体道祖神」があります。
真っ昼間から、まぁ、何と大胆な・・・。
どうしてこんなことになったのか、いつか取り調べをしてみたいものです。
【僧・戒定の供養塔】