「古堤」のすぐそばにあるのが、下町(しもちょう)の「諏訪神社」です。
看板の後半に書かれている「池鯉鮒(ちりふ→ちりゅう)大明神」は、本殿の後ろに祀られています。
この「池鯉鮒大明神」、もとは「諏訪神社」の南東、「甲大道南」というところに祀られていました。
「伝説之倉賀野」という本に、その謂れが載っています。
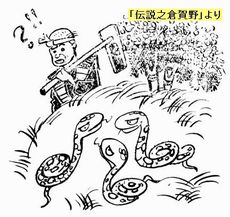
気も失わんばかりに驚いた農夫は、転げるようにして家に帰ると、翌朝から夢中になって木を伐り、材料を削って、一つの祠を作り上げます。
「諏訪神社」には、この他にも蛇にまつわる逸話がいくつか伝わっています。
そのひとつが「穴池の大蛇」という話です。
「諏訪神社」に蛇にまつわる話が多いのは、そもそも信州「諏訪大社」の本来の祭神が、白蛇の姿をしているとされる「ソソウ神」だということと無関係ではなさそうです。
また、蚕の繭を食べる鼠を蛇が食べることから、蚕室に「諏訪神社」のお札を貼る養蚕農家も多かったようです。
昔は今よりもずっと、蛇との関わりが身近だったのでしょうね。
看板の後半に書かれている「池鯉鮒(ちりふ→ちりゅう)大明神」は、本殿の後ろに祀られています。
この「池鯉鮒大明神」、もとは「諏訪神社」の南東、「甲大道南」というところに祀られていました。
「伝説之倉賀野」という本に、その謂れが載っています。
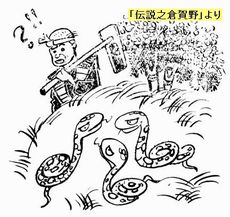
| 「ちぢり山」 | ||
| 「 | まむしが人を嚙じると言ふ事は聞いてゐたが、まむしが寄り集まって、今度は誰が誰を嚙じる番であると、嚙じる蛇と嚙られる人とが定(き)まってゐたと聞いては、全く驚かざるを得ない。 (略) | |
| 或る夏の夕暮れ、此邊で何時もまむしに嚙られるのだと言ふ事を知らない筈はない農夫が、圖らずも其處を通りかかって、怪我の功名とでも云はふか、まむしの相談の場所にぶつかって了(しま)った。 | |
| 所が通りかかったと云ふのが、怪我の功名だと思はれたその瞬間!眩惑と共に奈落の底にでも放り込まれる様な衝動を受けた。 | |
| 不思議と言はうか、皮肉と言はうか、今度嚙み殺される番に相談が定(き)まったのが、何と自分ではないか・・・。」 |
気も失わんばかりに驚いた農夫は、転げるようにして家に帰ると、翌朝から夢中になって木を伐り、材料を削って、一つの祠を作り上げます。
| 「 | その夢遊病者の様な彼によって作り上げられた祠は、その翌々日、甲大道南の地域に建てられた。 |
| 何の爲に此の祠を此の農夫が此の地に建てたかは、彼が其の後、あの凶惡なまむしの餌食にならないで済んだ事によって、御想像が願へると思ふ。 | |
| 此の祠を人呼んで『池鯉鮒大明神』といふ。まむし避けの神として祀られたものである。 | |
| 大明神の祠は、其後下町諏訪神社境内に移されたが、つい此の頃まで毎月一日に赤飯が、町の舊家の手によって供えられてゐたと言ふ事である。」 |
「諏訪神社」には、この他にも蛇にまつわる逸話がいくつか伝わっています。
そのひとつが「穴池の大蛇」という話です。
| 「穴池の大蛇」 | ||
| 「 | 今からずっと昔の事、儂(わし)が子供の頃だったよ。よく老人から云ひ聞かされたものだった。 | |
| あの御諏訪様の東北の方面が一帯の荒地で、其處に池があったさうだ。 其の池は、大昔随分廣くて深かったと言はれて居たが、段々と狭められて來た。 | ||
| 「 | |
| 「 | 今は此の邊一帯の地を『穴池』と云ってゐるが、此の穴池と云ふ言葉は、狭くても非常に深く、陥ち込めば穴の底の底までも引込まれるものだらうよ。 |
| 今でこそこの付近は豊沃な田や畑と變って居るが、今から五、六百年も前と言へば恐らく薄氣味惡い程の荒地で、土地の高低は勿論のこと、樹木の繫みは想像以上であったに相違ない。 さうした中に池の水がどんよりと不氣味な沈黙を續けてゐたものだらう。 「 |
|
| 其のうちに、此の池の中に、それはそれは恐ろしい大蛇が棲む様になった。 否、ずっと前からゐたのを知らなかったのかもわからない。 |
|
| ところが此の大蛇が段々と齢を經て來るに随って、人々の迷惑になる様な惡事をすると云ふことでなァ、これは何とかしなければなるまいと、寄り寄り相談した。 | |
| そして此の大蛇を退治して仕舞ふ事に定(き)まった。 | |
| それから下町の人達が随分と苦心した舉句、漸く之を退治したのぢゃ。ところが
見事打取っては見たものの、どう始末してよいかそれに困ってしまった。 「 |
|
| 思案の末、萬が一の崇りを恐れて、これは氏神の諏訪神社にあづけた方がよからうと云ふ事になって、此處へ奉納することになった。 斯うして大蛇も神に祀られたとの事ぢゃよ。」 |
(「伝説之倉賀野」より抜粋)
「諏訪神社」に蛇にまつわる話が多いのは、そもそも信州「諏訪大社」の本来の祭神が、白蛇の姿をしているとされる「ソソウ神」だということと無関係ではなさそうです。
また、蚕の繭を食べる鼠を蛇が食べることから、蚕室に「諏訪神社」のお札を貼る養蚕農家も多かったようです。
昔は今よりもずっと、蛇との関わりが身近だったのでしょうね。
【倉賀野下町の諏訪神社】



















