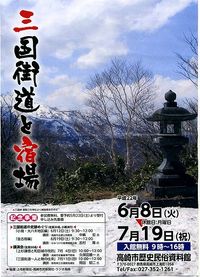「大八木の高燈台」からさらに東へ200mほど行くと、大八木町公民館です。
「大八木の高燈台」からさらに東へ200mほど行くと、大八木町公民館です。その駐車場の片隅に、「大日堰頌徳碑」というのが建っています。
碑文によると、「大日堰(だいにちぜき)」と呼ばれる用水が開鑿されたのは、明暦元年(1655)だそうです。
それ以前は、
「八木邑の水田数十町歩は累年灌漑に苦しみ水争絶えず
逃散相次ぎ郷土の荒廃里人の窮乏其の極に達す」
という状態だったようです。
この窮状を見かね、
「高崎藩主安藤對馬守の援助を得て井野川よりの用水路開鑿を企図し
挺身設計測量の事に當(あた)」
ったのが、名主・静利右衛門翁です。
承應二年(1653)に着手した工事は、
「翁の斯かる崇高な意氣に感じ大八木下小鳥浜尻貝沢の邑人
老若男女を問はず此の偉業に協力」
し、三ヵ年に及ぶ難工事をついに竣工させました。
「翁は之(これ)偏(ひと)へに傍に安置せる
大日如来の加護に依ると信じ大日堰と称し」
たのだそうです。
さて、その「大日堰」とはどこなのでしょう。
 一番近くを流れるのは、大八木南交差点の半鐘櫓下の水路です。
一番近くを流れるのは、大八木南交差点の半鐘櫓下の水路です。向こう側(西)から流れてくる水は、ここで二股に分かれます。
これを上流へ遡ってみることにしました。
 三面コンクリートの水路が多い中、石垣積みのこの水路、なかなかいい雰囲気です。
三面コンクリートの水路が多い中、石垣積みのこの水路、なかなかいい雰囲気です。
水路を遡って追跡すること約1km、「大日堰揚堰水門」と書かれた水門に出ました。
辿った水路が思った通り「大日堰」であったことに、ちょっぴり喜びを感じた瞬間でしたが、ちょっぴり疑問も感じました。
「大日堰頌徳碑」には「井野川よりの用水路開鑿」とあるのに、この川は「井野川」ではなく、「早瀬川」です。
 辺りをうろついてみると、ちょうど取水口の反対側に、「早瀬川」に流れ込んでいる、怪しい(?)水路がありました。
辺りをうろついてみると、ちょうど取水口の反対側に、「早瀬川」に流れ込んでいる、怪しい(?)水路がありました。この水路を追跡したいところですが、高崎経済大学付属高校とラジエ工業の敷地に入ってしまい、それができません。
しかたなく地図上で追ってみると、浜川運動公園を抜けて井野川につながっているように見えます。
おそらくここが、明暦元年に開鑿したという、「大日堰」の取り入れ口ではないかと見当をつけました。
 浜川運動公園側に回って、それらしい水路を辿って行くと、体育館と陸上競技場の脇を抜けて、井野川の土手に出ました。
浜川運動公園側に回って、それらしい水路を辿って行くと、体育館と陸上競技場の脇を抜けて、井野川の土手に出ました。 ←ここが、取水口の水門です。
←ここが、取水口の水門です。それにしても、ずいぶん遠い所から取水したものだと思いますが、井野川というのは結構谷が深いのです。
ここまで上流からでないと、用水の落差が取れなかったのでしょう。
大変な工事だったと思います。
ところで、「大日堰頌徳碑」文中の「傍らに安置せる大日如来」は、ここまでの間に見当たりませんでした。
いったい何処にあるのでしょうか?
そのお話は、また次回ということに。
【大日堰頌徳碑】
【大日堰揚堰水門】
【大日堰井野川取水口】