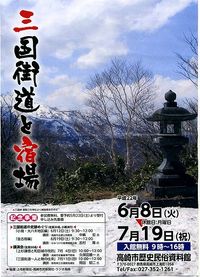「三ツ寺堤」の西側には、一里塚のように小高くなっている所があり、いくつもの庚申塔が建っています。
「三ツ寺堤」の西側には、一里塚のように小高くなっている所があり、いくつもの庚申塔が建っています。広大な圃場のおかげで、遠く榛名の山並みまで見通すことができます。
かつて旧三国街道を行き来した旅人達が、同じ風景を眺めていたかと思うと、感慨深いものがあります。
 庚申塔の中に、一番大きくて面白い形をしたものがあります。
庚申塔の中に、一番大きくて面白い形をしたものがあります。面白いのは、形だけではありません。
中央の三文字、いったい何と書いてあるのでしょう?
どうにも分からず、近くの「かみつけの里博物館」へ行ってみました。
あいにく館長さんがお留守で、古代専門の職員さんしかいらっしゃらず、謎は解けませんでした。
ふと思いついて、その足で前橋の県立文書館へ行ってみました。
閉館ぎりぎりに飛び込んで、写真を見てもらったのですが、やはり分からないようでした。
でも、さすが普段古文書を扱っている職員さんです。
「庚申塔」をキーワードにして、それらしい言葉を探し出してくれました。
それが、「青面王(しょうめんおう)」です。
「庚申塔」には「庚申」と刻まれているものが多い中、「青面金剛(しょうめんこんごう)」と刻まれているものも少なくありません。
「青面金剛」は、もともと疫病を流行らす恐ろしい神様ですが、民間の庚申信仰においては、「三尸の虫(さんしのむし)」を抑える神として祀られています。
これも、「禍と福は裏と表」の類ですね。
ともあれ、「青面金剛」は浅学な私でも知っていたのですが、「青面王」というのは、恥ずかしながら初めて聞きました。
ただ、それにしても不思議なのは、「青面王」という文字は、篆書体ではこのようになるはずです。 →
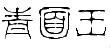

「面」と「王」はいいでしょうが、
「青」の字の両側の波線は余分でしょう。→
しかし、これには心当たりがありました。
実は、新保田中の道祖神で、同じようなのを見たことがあるんです。
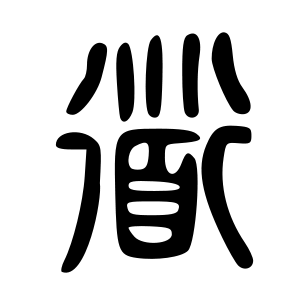 「道」の本字「衟」を、篆書体にすると、
「道」の本字「衟」を、篆書体にすると、←こうなります。
 これを、新保田中の道祖神では、
これを、新保田中の道祖神では、←こんな風に刻んであるのです。
ちょっと、ブログに掲載していいのかどうか躊躇しますが、女性の象徴を模しているのだそうです。
どうですか、庚申塔の「青」の字と似ているでしょう?
「道祖神」には、このように男女の象徴を模したものが少なくありません。
以前「おちゃめ!」の記事でご紹介したのも、そうでした。
これには、諸説様々ありますが、道の分去りの「二股」から連想したとか、男女の営みが子孫繁栄・五穀豊穣につながるとか・・・。
そこで、三ツ寺の庚申塔の「青」の話に戻りますが、両側の波線は、おそらく女性のボディラインを表しています。
そして、その中にある「青」の字は、女性の象徴を模しているのだと思います。
昔の人は何事も、良い方に、良い方に考えたのですね。
きっと、厳しく辛い暮らしの中から編み出された、禍を福とする知恵だったのでしょう。
見習いたいものです。
【三ツ寺堤の庚申塔】