飯塚の追分を左に入る旧三国街道を進むと、突然目の前に大河が現れます。
流れているのは、水ならぬ自動車。
昭和四十一年(1966)に開通した「高前バイパス」が、旧三国街道を分断し、向こう岸へ渡るにはしばし待たねばなりません。
 「高前バイパス」を渡って200mほど行くと、四つ辻になりますが、
「高前バイパス」を渡って200mほど行くと、四つ辻になりますが、
←昔、この辺を「続橋(つづきばし)」と呼んでいたそうです。
近くで農作業をしているお年寄りにお聞きすると、橋のことをご存知でした。
「橋ったって、大したんじゃねえんだよ。
川が3本あって、あっちからも、こっちからも
渡れるようになってたんだ。」
お話からすると、橋が何本も架かっていた訳ではなく、1本の橋が3本の川を跨ぐように架かっていたようです。
それにしても、昔の人は粋な名前を付けるものですね。
 分去りには道祖神が付き物ですが、ここにも安永九年(1780)に建てられた道祖神が建っています。
分去りには道祖神が付き物ですが、ここにも安永九年(1780)に建てられた道祖神が建っています。
今は、道祖神の前を西に向かう道が通っていますが、昔の地図を見ると、この道ではなく、斜めに北西に向かう道が描かれています。
 現在、その道は消えてしまいましたが、昭和五十三年(1980)発行の「高崎の散歩道 第六集」には、
現在、その道は消えてしまいましたが、昭和五十三年(1980)発行の「高崎の散歩道 第六集」には、
「ここから細い道を北上すると蓮花院の入り口に出る。自動車も通れないほどの道で散歩道としては最適である。」
と、記述されていますので、少なくともこの頃までは残っていたようです。
でも、実は、昔の道が消えずに残っているところがあります。
ちょっと道幅は広くなったようですが、「幸宮(さちのみや)神社」に行く道が、それです。
 「幸宮神社」。
「幸宮神社」。
なんと、素敵な名前でしょう。
でも、謎満載の神社です。
由緒によると、永仁六年(1298)に天皇の命により、従五位「魚取明神」として奉られた、とありますが、それなら「魚取神社」とでもすれば良さそうなものですが・・・。
そもそも「魚取社」のご祭神は「えびす様」ですが、「幸宮神社の」ご祭神は「猿田彦命(サルタヒコノミコト)」で、副祭神は「彦火火出見命(ヒコ・ホホデミノミコト)」です。
う~ん、わかりません。
斯くなる上は、迷道院が無理やりこじ付けてみるしかありません。
「幸宮神社」のご祭神「猿田彦命」は、天孫「瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)」が天降る時、松明をかざして道案内をしたという神です。
そして、その「瓊瓊杵尊」と「木花開耶姫(コノハナノ・サクヤヒメ)」との間に生まれたのが、「彦火火出見命」です。
余談ですが、一夜を共にしただけで身籠ったので、「瓊瓊杵尊」に「本当に俺の子か?」と疑われた「木花開耶姫」が、それを証明するために、燃え盛る火の中で産んだという、物凄い生まれ方をした神です。
さらに、この「彦火火出見命」は、「海幸・山幸」の神話に出てくる「山幸彦」だという話もあります。
「山幸彦」は、兄の「海幸彦」に借りた釣り針を失くしてしまいますが、その釣り針を喉に引っ掛けていたのが、鯛だったんですね。
では、「魚取社」のご祭神「えびす様」が脇に抱えているのは、何でしょう?
そう!鯛ですよね!
ほらほらほらっ!つながってきたでしょ!
「幸宮神社→猿田彦命→瓊瓊杵尊→彦火火出見命→山幸彦→鯛→えびす様→魚取社」
ねっ!
こじ付けついでに、もうひとつ。
「えびす様」は、「少彦名命(スクナヒコナノミコト)」だという説もあります。
「大国主命(オオクニヌシノミコト)」つまり「だいこく様」と一緒に、国造りをしたという神話からです。
「少彦名命」は、国造りが終わった後、「粟島(あわしま)」という島から「常世の国(とこよのくに)」に弾き飛んだと言われています。
そこから、全国にある「淡島(あわしま)神社」では、「少彦名命」を祀っているところが多いようです。
 実は、ここ「幸宮神社」にも「淡島神社」が祀られているんです。
実は、ここ「幸宮神社」にも「淡島神社」が祀られているんです。
(因みに、この字は高崎藩最後の殿様、大河内輝声(てるな)の揮毫だそうです。)
「淡島神」は、婦人病治癒を始めとして安産・子授けなど、女性に関するあらゆることに霊験があると言われます。
「幸宮神社」には、この他にも沢山の神様が祀られています。
「石尊大権現」、「御嶽大権現」、「摩利支天」に、相撲の神様「野見宿禰命(ノミノスクネノミコト)」まで。
これだけ神様が揃っていれば、人生のほとんどの御利益は得られそうです。
村人が、「幸宮神社」と呼んだ理由も、分かるような気がします。
流れているのは、水ならぬ自動車。
昭和四十一年(1966)に開通した「高前バイパス」が、旧三国街道を分断し、向こう岸へ渡るにはしばし待たねばなりません。
 「高前バイパス」を渡って200mほど行くと、四つ辻になりますが、
「高前バイパス」を渡って200mほど行くと、四つ辻になりますが、←昔、この辺を「続橋(つづきばし)」と呼んでいたそうです。
近くで農作業をしているお年寄りにお聞きすると、橋のことをご存知でした。
「橋ったって、大したんじゃねえんだよ。
川が3本あって、あっちからも、こっちからも
渡れるようになってたんだ。」
お話からすると、橋が何本も架かっていた訳ではなく、1本の橋が3本の川を跨ぐように架かっていたようです。
それにしても、昔の人は粋な名前を付けるものですね。
 分去りには道祖神が付き物ですが、ここにも安永九年(1780)に建てられた道祖神が建っています。
分去りには道祖神が付き物ですが、ここにも安永九年(1780)に建てられた道祖神が建っています。今は、道祖神の前を西に向かう道が通っていますが、昔の地図を見ると、この道ではなく、斜めに北西に向かう道が描かれています。
 現在、その道は消えてしまいましたが、昭和五十三年(1980)発行の「高崎の散歩道 第六集」には、
現在、その道は消えてしまいましたが、昭和五十三年(1980)発行の「高崎の散歩道 第六集」には、「ここから細い道を北上すると蓮花院の入り口に出る。自動車も通れないほどの道で散歩道としては最適である。」
と、記述されていますので、少なくともこの頃までは残っていたようです。
でも、実は、昔の道が消えずに残っているところがあります。
ちょっと道幅は広くなったようですが、「幸宮(さちのみや)神社」に行く道が、それです。
 「幸宮神社」。
「幸宮神社」。なんと、素敵な名前でしょう。
でも、謎満載の神社です。
由緒によると、永仁六年(1298)に天皇の命により、従五位「魚取明神」として奉られた、とありますが、それなら「魚取神社」とでもすれば良さそうなものですが・・・。
そもそも「魚取社」のご祭神は「えびす様」ですが、「幸宮神社の」ご祭神は「猿田彦命(サルタヒコノミコト)」で、副祭神は「彦火火出見命(ヒコ・ホホデミノミコト)」です。
う~ん、わかりません。
斯くなる上は、迷道院が無理やりこじ付けてみるしかありません。
「幸宮神社」のご祭神「猿田彦命」は、天孫「瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)」が天降る時、松明をかざして道案内をしたという神です。
そして、その「瓊瓊杵尊」と「木花開耶姫(コノハナノ・サクヤヒメ)」との間に生まれたのが、「彦火火出見命」です。
余談ですが、一夜を共にしただけで身籠ったので、「瓊瓊杵尊」に「本当に俺の子か?」と疑われた「木花開耶姫」が、それを証明するために、燃え盛る火の中で産んだという、物凄い生まれ方をした神です。
さらに、この「彦火火出見命」は、「海幸・山幸」の神話に出てくる「山幸彦」だという話もあります。
「山幸彦」は、兄の「海幸彦」に借りた釣り針を失くしてしまいますが、その釣り針を喉に引っ掛けていたのが、鯛だったんですね。
では、「魚取社」のご祭神「えびす様」が脇に抱えているのは、何でしょう?
そう!鯛ですよね!
ほらほらほらっ!つながってきたでしょ!
「幸宮神社→猿田彦命→瓊瓊杵尊→彦火火出見命→山幸彦→鯛→えびす様→魚取社」
ねっ!
こじ付けついでに、もうひとつ。
「えびす様」は、「少彦名命(スクナヒコナノミコト)」だという説もあります。
「大国主命(オオクニヌシノミコト)」つまり「だいこく様」と一緒に、国造りをしたという神話からです。
「少彦名命」は、国造りが終わった後、「粟島(あわしま)」という島から「常世の国(とこよのくに)」に弾き飛んだと言われています。
そこから、全国にある「淡島(あわしま)神社」では、「少彦名命」を祀っているところが多いようです。
 実は、ここ「幸宮神社」にも「淡島神社」が祀られているんです。
実は、ここ「幸宮神社」にも「淡島神社」が祀られているんです。(因みに、この字は高崎藩最後の殿様、大河内輝声(てるな)の揮毫だそうです。)
「淡島神」は、婦人病治癒を始めとして安産・子授けなど、女性に関するあらゆることに霊験があると言われます。
「幸宮神社」には、この他にも沢山の神様が祀られています。
「石尊大権現」、「御嶽大権現」、「摩利支天」に、相撲の神様「野見宿禰命(ノミノスクネノミコト)」まで。
これだけ神様が揃っていれば、人生のほとんどの御利益は得られそうです。
村人が、「幸宮神社」と呼んだ理由も、分かるような気がします。
【続橋の道祖神】
【幸宮神社】





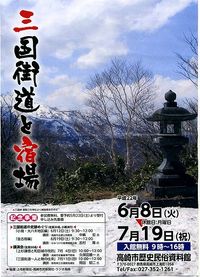


 at 2009年12月02日 18:52
at 2009年12月02日 18:52





