 柳家紫文師匠から、すんっごく素敵なストラップを頂戴しました。
柳家紫文師匠から、すんっごく素敵なストラップを頂戴しました。8月8日(日)に東京の谷中にある「全生庵」(ぜんしょうあん)で、落語協会恒例の「圓朝まつり」というのが開かれました。
そこでは芸人さん達による「芸人屋台」というのがあって、紫文師匠は「小間物シモン堂」という店を出したのだそうです。
大人気だったようで、用意したものは全て完売したとのことですが、有り難いことに、その中から確保して送って頂いたのです。
私如き者に、このような貴重なものを送って下さったのは、ストラップに「高崎扇」(たかさきおうぎ)という紋がデザインされているので、ということでした。
でも、紫文師匠が高崎出身だから「高崎扇」という訳ではないのです。
 「圓朝まつり」の所以である名人・三遊亭圓朝、そしてその一門の三遊派の芸人さんは、みな、この「高崎扇」の紋付きを着て、高座に上がっているのです。
「圓朝まつり」の所以である名人・三遊亭圓朝、そしてその一門の三遊派の芸人さんは、みな、この「高崎扇」の紋付きを着て、高座に上がっているのです。三遊亭圓朝は、墓所が東京谷中の全生庵であることで分かるように、生まれも活躍の場も江戸、東京です。
その圓朝の紋どころが、なぜ「高崎扇」なんでしょう?
 そもそも、「高崎扇」とはどんな紋なんでしょう?
そもそも、「高崎扇」とはどんな紋なんでしょう?「高崎扇」は、高崎藩主・大河内松平家の替紋(かえもん)として用いられています。
替紋というのは、公式的な家紋以外に、分家が独自の家紋として使っているものです。
では、大河内氏の公式な家紋は何かというと、よく「浮線蝶」(ふせんちょう)と言われていますが、正しくは「臥蝶(ふせちょう)に十六菊」という紋です。
高崎城址発掘時に出てきたという、鬼瓦に刻まれているのがこの紋です。
さて、この「高崎扇」と、三遊亭圓朝の関係です。
圓朝は、天保十年(1839)初代・橘家圓太郎と母・なかとの間に産まれます。
この母・なかが前夫との間につくった子ども、つまり圓朝の義兄にあたるのが、江戸小石川にある「是照院」(ぜしょういん)の十五世住職・永泉玄昌禅師でした。
「是照院」は、寛文三年(1663)に開山されましたが、享保年間(1716~35)の度重なる大火で、類焼の難に遭ってしまいます。
これを援助し再興させたのが、高崎藩主・大河内松平右京太夫輝貞公でした。
以来、「是照院」は高崎藩藩士の菩提寺として護持されてゆくことになり、右京太夫輝貞公を中興の祖としています。
このことから、「是照院」の寺紋もまた「高崎扇」なのです。
圓朝は、義兄の務める「是照院」で見た「高崎扇」の紋が気に入ったのでしょう。
落語家の大事な小道具「扇」をあしらっていること、そして「扇」は末広がりで縁起がいいことなどが、その理由だろうと思います。
そこで、この「高崎扇」を自身の紋として使うことを希望して、高崎藩に許可を願い出たところ、時の藩主・大河内 輝声(てるな)から羽織を拝領し、以来、「高崎扇」を高座着に付けるようになったということです。
(参考:「是照院」HP)

←このマークは、何のマークかご存知でしょうか。
これは、高崎経済大学の学章です。
このマークも、「高崎扇」を元にデザインされているそうです。
 ←こんなTシャツだってあります。
←こんなTシャツだってあります。(三遊亭遊喜師匠のブログより)
「高崎扇亭」は、平成二十年(2008)の「緑化フェア」期間中に行われた、、「高崎まちなか寄席」の会場、旧名曲喫茶「あすなろ」です。
しかし翌年、「高崎まちなか寄席」は開かれたものの、「高崎扇亭」は会場とならず、平成22年には「高崎まちなか寄席」も開かれなくなってしまったようです。
紫文師匠は嘆きます。
「高崎藩主が名人三遊亭圓朝のバックで紋まであげたというのは、
高崎の文化都市としての宣伝には最高なんですがねえ。
六文銭のように「武勇」でなく、芸人、「文化」で名高い、
というのが商都高崎としていいと思うんですが…」
「そうそう「まちなか寄席」の幟、法被には高崎扇が入ってました。
ただそれを情報として発信していない、つたえられない、
故にだれも知らないというのが、高崎の現状ですよねえ。」
と。
その一人が、高崎市観光課のKさん。
もう一人が、高崎青年会議所のSさん。
どちらの方も、大の落語ファンです。
また、圓朝の噺には、上州がよく舞台となります。
グンブロガー、風子さんの記事にも出てくる「安中草三郎」。
その他にも、「霧陰伊香保湯煙」とか、「塩原多助旅日記」という噺もあります。
斯くの如く、三遊亭圓朝と高崎は因縁浅からぬものがあり、そのシンボル「高崎扇」もいろいろな所で活躍しています。
城下町高崎のシンボルとして、「高崎扇」にもっと光を当てても良いのではないでしょうか。



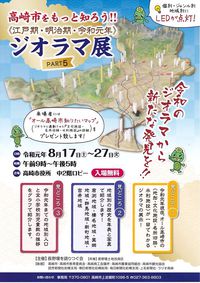

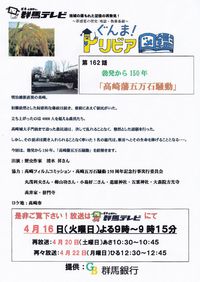

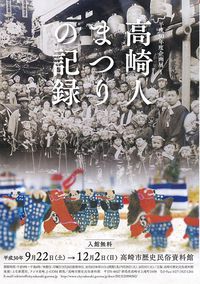
 at 2010年08月18日 23:02
at 2010年08月18日 23:02





