昨年の12月、「次」か「治」か?の記事に、高崎市史編纂委員の中村茂先生から、こんなコメントを頂きました。
「九蔵町大雲寺に武田信玄の軍師山本勘助の子孫の墓があるので、宣伝して下さい。
墓には「菅助」とありますが、「次」「治」と同じく、文字が違っても一向に差し支えありません。甲陽軍鑑が「勘」を使ったので、その後の書物が「勘」を使用しているのです。
山本家は山城国淀藩に仕えたが、改易のため浪人となり、大河内家の祖松平信興の土浦藩に就職しました。
近く、群馬の森の県立博物館の黒田館長が、館長講座で高崎藩士山本家の由緒を発表します。」
えぇっ!?と思いました。
山本勘助って、川中島の合戦で戦死したはず。
その子孫の墓が高崎にあって、墓には「菅助」と書いてある?
頭の中、ぐじゃぐじゃです。
で、待ち遠しい思いで待っていた、県立歴史博物館・黒田日出男館長の講座「山本勘助の江戸時代」を、3月6日(土)に聞きに行ってきました。
黒田館長のお話では、山本勘助はつい最近まで、架空の人物であるというのが近代歴史学の定説となっていたと言います。
ところが、平成二十一年(2009)六月、安中市原市で薬屋を営んでいた真下家から、山本勘助実在を証明できる可能性のある書状が見つかったのだそうです。
調べたら、6月11日の上毛新聞に、載っていましたのでご覧ください。
この文書は、明治維新により禄を失った山本家が、生活のために甲冑などと共に手放したものであろうということです。
それが、安中の真下珂十郎の入手するところとなり、真下家所蔵文書として伝来したのだろうという訳です。
実はこの文書、明治二十五年(1892)に東京大学史料編纂所へ持ち込まれたことがあるのです。
持ち込んだのは、山本菅助の十三代目にあたる山本喜三氏でした。
ところが、原本は既に売却されていたため、持参したのがその写しだったことから、「偽文書」扱いされてしまったのです。
もしもその時、原本が持ち込まれていたなら、山本菅助架空人物説は崩れていたでしょう。
その原本が、今になって見つかったのですから、大騒ぎです。
黒田館長は、
「もはや、山本菅助を架空・虚構の人物とすることは絶対にできない。
近現代の歴史学の方が不明を恥じ、菅助に謝らなければならないのである。
これは、歴史学が生み出した冤罪だったのだ。」
と仰っています。
因縁めいた話ですが、黒田館長は元・東京大学史料編纂所長をされていたのです。
さて、山本菅助と高崎の関係ですが、四代目山本菅助※1(晴方)が松平家に奉公したことで、元禄八年(1695)松平輝貞が壬生から高崎城主として転封されたのに伴い、菅助も五代目以降十二代目の明治維新まで高崎藩に仕えることになりました。
コメントを下さった中村茂先生は、高崎藩史の地道な研究の過程で、藩士の墓を一つひとつ調査・研究されています。
その中で、山本菅助の墓を発見されたということで、黒田館長もそのお仕事を高く評価されていました。
 雨の大雲寺へ、菅助の墓を探しに行きました。
雨の大雲寺へ、菅助の墓を探しに行きました。
正面に「山本菅助之墓」と刻まれてばかりいると思って、墓地を一回りしましたが、見つかりません。
二回り目でやっと見つけました。

 ←この一角が、山本家の墓地です。
←この一角が、山本家の墓地です。
写真が下手で、よく分からないかもしれませんが、「山本菅助入道道鬼七世孫 山本菅助菅原晴生」と刻まれています。→
高崎のこの一角に、伝説上の人物と言われてきた山本菅助の子孫が眠っているのです。
すごいことではありませんか!
歴史を塗り替えることになるこの遺跡を、高崎市が持っていたことに、驚きと、誇りを感じます。
そして、その貴重な歴史遺産を掘り起こして下さった、中村茂先生と、黒田日出男館長に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
最後に、心に残った黒田館長の言葉をご紹介いたします。
「歴史研究は時間との戦いです。
今この瞬間にも、歴史資料はどんどん失われています。
論文を書くことが歴史研究の仕事ではありません。
歴史資料を確保し、残すことが
歴史研究の最も大切な仕事です。」
「九蔵町大雲寺に武田信玄の軍師山本勘助の子孫の墓があるので、宣伝して下さい。
墓には「菅助」とありますが、「次」「治」と同じく、文字が違っても一向に差し支えありません。甲陽軍鑑が「勘」を使ったので、その後の書物が「勘」を使用しているのです。
山本家は山城国淀藩に仕えたが、改易のため浪人となり、大河内家の祖松平信興の土浦藩に就職しました。
近く、群馬の森の県立博物館の黒田館長が、館長講座で高崎藩士山本家の由緒を発表します。」
えぇっ!?と思いました。
山本勘助って、川中島の合戦で戦死したはず。
その子孫の墓が高崎にあって、墓には「菅助」と書いてある?
頭の中、ぐじゃぐじゃです。
で、待ち遠しい思いで待っていた、県立歴史博物館・黒田日出男館長の講座「山本勘助の江戸時代」を、3月6日(土)に聞きに行ってきました。
黒田館長のお話では、山本勘助はつい最近まで、架空の人物であるというのが近代歴史学の定説となっていたと言います。
ところが、平成二十一年(2009)六月、安中市原市で薬屋を営んでいた真下家から、山本勘助実在を証明できる可能性のある書状が見つかったのだそうです。
調べたら、6月11日の上毛新聞に、載っていましたのでご覧ください。
この文書は、明治維新により禄を失った山本家が、生活のために甲冑などと共に手放したものであろうということです。
それが、安中の真下珂十郎の入手するところとなり、真下家所蔵文書として伝来したのだろうという訳です。
実はこの文書、明治二十五年(1892)に東京大学史料編纂所へ持ち込まれたことがあるのです。
持ち込んだのは、山本菅助の十三代目にあたる山本喜三氏でした。
ところが、原本は既に売却されていたため、持参したのがその写しだったことから、「偽文書」扱いされてしまったのです。
もしもその時、原本が持ち込まれていたなら、山本菅助架空人物説は崩れていたでしょう。
その原本が、今になって見つかったのですから、大騒ぎです。
黒田館長は、
「もはや、山本菅助を架空・虚構の人物とすることは絶対にできない。
近現代の歴史学の方が不明を恥じ、菅助に謝らなければならないのである。
これは、歴史学が生み出した冤罪だったのだ。」
と仰っています。
因縁めいた話ですが、黒田館長は元・東京大学史料編纂所長をされていたのです。
さて、山本菅助と高崎の関係ですが、四代目山本菅助※1(晴方)が松平家に奉公したことで、元禄八年(1695)松平輝貞が壬生から高崎城主として転封されたのに伴い、菅助も五代目以降十二代目の明治維新まで高崎藩に仕えることになりました。
| ※1 | 三代目・山本菅助が、寛永十年(1633)下総古河城主・永井信濃守に仕えた折、代々山本菅助を名乗れと命じられ、以降、山本家当主は代々菅助を名乗る。 |
コメントを下さった中村茂先生は、高崎藩史の地道な研究の過程で、藩士の墓を一つひとつ調査・研究されています。
その中で、山本菅助の墓を発見されたということで、黒田館長もそのお仕事を高く評価されていました。
 雨の大雲寺へ、菅助の墓を探しに行きました。
雨の大雲寺へ、菅助の墓を探しに行きました。正面に「山本菅助之墓」と刻まれてばかりいると思って、墓地を一回りしましたが、見つかりません。
二回り目でやっと見つけました。

 ←この一角が、山本家の墓地です。
←この一角が、山本家の墓地です。写真が下手で、よく分からないかもしれませんが、「山本菅助入道道鬼七世孫 山本菅助菅原晴生」と刻まれています。→
高崎のこの一角に、伝説上の人物と言われてきた山本菅助の子孫が眠っているのです。
すごいことではありませんか!
歴史を塗り替えることになるこの遺跡を、高崎市が持っていたことに、驚きと、誇りを感じます。
そして、その貴重な歴史遺産を掘り起こして下さった、中村茂先生と、黒田日出男館長に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
最後に、心に残った黒田館長の言葉をご紹介いたします。
「歴史研究は時間との戦いです。
今この瞬間にも、歴史資料はどんどん失われています。
論文を書くことが歴史研究の仕事ではありません。
歴史資料を確保し、残すことが
歴史研究の最も大切な仕事です。」
【大雲寺 山本菅助子孫の墓】



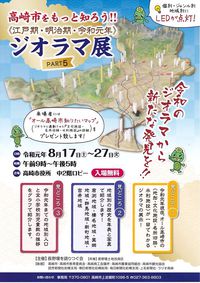

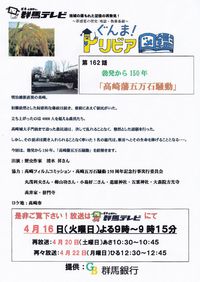

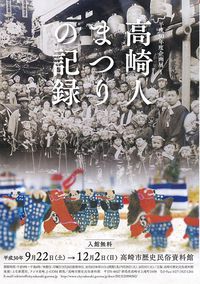
 at 2010年03月08日 06:10
at 2010年03月08日 06:10





