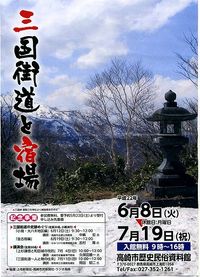旧三国街道を辿りながら、高崎と前橋の境界まで達したところで、一路、新三国街道(高崎・渋川線)で帰ることにしました。
 棟高の信号を過ぎて300mほど行った所に、「観音寺」がありましたので、寄ってみました。
棟高の信号を過ぎて300mほど行った所に、「観音寺」がありましたので、寄ってみました。
「観音寺」と呼ばれていますが、上野国寺院明細帳によると「観音堂」となっており、なぜか前橋市元総社町の長見寺持ちになっています。
元はここに寺があったと言われていますが、いつの時代か焼失したと伝えられる、由緒不詳の寺です。
現在の「観音堂」は、後に近隣の人々が再建したものだそうです。
徳川時代から明治初期にかけて、「観音堂」の大門を馬場に使った奉納競馬が行われていて、別名「競馬観音」とも呼ばれていたそうです。
馬場は、明治十四年(1881)、清水越え三国街道開通の際、旧群馬町農協本所辺りに移設され本格的な回り馬場になると、「観音寺競馬」として知れ渡り、県内各地から見物客や競走馬の参加があったそうです。
開催日の前には、村の若い衆が自転車に乗って、遠く伊香保までビラを貼りに行ったといいます。
そんな関係もあってか、「観音堂」後ろの「猪土堤」上には、「騎手 桑原千次郎君碑」や「日露戦役 殉難軍馬彰功碑」といった、馬に関する石碑が建っています。
 境内には、もうひとつ立派なお堂があります。
境内には、もうひとつ立派なお堂があります。
弘法大師をお祀りする「大師堂」です。

失礼して、内部を撮影させてもらいました。
壇上に沢山並んでいるのは、信者が奉納した大師像です。
この「大師堂」が建立されたのは、万延元年(1860)と言われていますが、その時、般若経の経典六百巻が奉納されました。
境内には、大切な経典を収蔵する蔵がないため、家に土蔵のある信徒が持ち回りで、100年以上も経典を守り続けてきたそうです。
しかし、時を経て蔵を持つ家も少なくなり、さりとて境内に蔵を建てる予算もなく、困っておりました。

そんな中、村民の飯島富雄氏が古希の記念にと、私財を投じて昭和六十二年(1987)に建立・寄贈したのが、この「経蔵」です。
この飯島富雄氏は、「旧三国街道 さ迷い道中記(13)」の中に出てくる、「天王山薬師院徳昌寺」を編集した人物です。
なかなか、できることではありません。頭の下がる思いがします。
境内には、もうひとつ、面白いものがあります。
それは、次回のお楽しみ。
 棟高の信号を過ぎて300mほど行った所に、「観音寺」がありましたので、寄ってみました。
棟高の信号を過ぎて300mほど行った所に、「観音寺」がありましたので、寄ってみました。「観音寺」と呼ばれていますが、上野国寺院明細帳によると「観音堂」となっており、なぜか前橋市元総社町の長見寺持ちになっています。
元はここに寺があったと言われていますが、いつの時代か焼失したと伝えられる、由緒不詳の寺です。
現在の「観音堂」は、後に近隣の人々が再建したものだそうです。
徳川時代から明治初期にかけて、「観音堂」の大門を馬場に使った奉納競馬が行われていて、別名「競馬観音」とも呼ばれていたそうです。
馬場は、明治十四年(1881)、清水越え三国街道開通の際、旧群馬町農協本所辺りに移設され本格的な回り馬場になると、「観音寺競馬」として知れ渡り、県内各地から見物客や競走馬の参加があったそうです。
開催日の前には、村の若い衆が自転車に乗って、遠く伊香保までビラを貼りに行ったといいます。
そんな関係もあってか、「観音堂」後ろの「猪土堤」上には、「騎手 桑原千次郎君碑」や「日露戦役 殉難軍馬彰功碑」といった、馬に関する石碑が建っています。
 境内には、もうひとつ立派なお堂があります。
境内には、もうひとつ立派なお堂があります。弘法大師をお祀りする「大師堂」です。

失礼して、内部を撮影させてもらいました。
壇上に沢山並んでいるのは、信者が奉納した大師像です。
この「大師堂」が建立されたのは、万延元年(1860)と言われていますが、その時、般若経の経典六百巻が奉納されました。
境内には、大切な経典を収蔵する蔵がないため、家に土蔵のある信徒が持ち回りで、100年以上も経典を守り続けてきたそうです。
しかし、時を経て蔵を持つ家も少なくなり、さりとて境内に蔵を建てる予算もなく、困っておりました。

そんな中、村民の飯島富雄氏が古希の記念にと、私財を投じて昭和六十二年(1987)に建立・寄贈したのが、この「経蔵」です。
この飯島富雄氏は、「旧三国街道 さ迷い道中記(13)」の中に出てくる、「天王山薬師院徳昌寺」を編集した人物です。
なかなか、できることではありません。頭の下がる思いがします。
境内には、もうひとつ、面白いものがあります。
それは、次回のお楽しみ。
(参考図書:「群馬町誌」「観音寺誌」)
【棟高観音寺 観音堂】