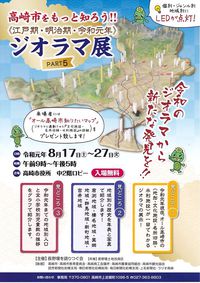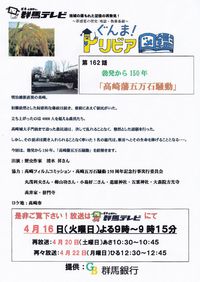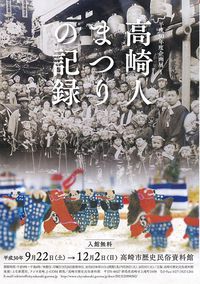旧群馬町足門に新しくオープンした「高崎市市民活動センター(ソシアス)」で、「高崎学検定プレ講座」を受講してきました。
旧群馬町足門に新しくオープンした「高崎市市民活動センター(ソシアス)」で、「高崎学検定プレ講座」を受講してきました。定員250名に対し応募者は500人を超えたということで、関心の高さを感じます。
第1回のプレ講座にも応募したのですが、くじ運の悪い迷道院は案の定落選し、今度もどうせダメだろうと思っていましたが、何の風の吹き回しか当選してしまいました。
それにしても、高崎だけでもこれだけの人が歴史に関心を持っているということは、全国ではどのくらいになるのでしょう。
高崎が「歴史の町」として認知してもらえたら、どのくらい人がやって来ることか。
これを、町の観光に使わない手はありませんよね。
11月に予定されている「高崎学検定試験」は、日本一難しい検定を目指しているそうで、合格するのは100人中3人程度だとか。
てなことで、興味偏在、暗記能力ゼロの迷道院は、はなから諦めてるような訳ですが・・・。
 第2回プレ講座の講師は、いつもお世話になっている中村茂先生でした。
第2回プレ講座の講師は、いつもお世話になっている中村茂先生でした。演題は「高崎五万石騒動 明治二年という年」。
お話しの中で、ブログ仲間・いちじんさん所属の「高崎五万石騒動研究会」の活動が、度々紹介されていました。
講座は中村先生らしく、多数の古文書を根拠にしたお話しで、とても興味深いものがありました。
例えば、明治二年(1869)十月十八日に、農民四千人余りが請願書提出のために高崎城へ押し出した時、講金世話役・関根作右衛門が農民に同情して、先頭に立って炊出しの世話をしたと言われている件ですが。
そのくだりは、細野格城氏著「高崎五万石騒動」(現代語訳:佐藤行男氏)に、こう書かれています。
| 「 | この時連雀町の関根作右衛門氏は大いに百姓側に同情を表され、百姓に昼食を出してやろうと同役の御用達講金世話役達へ早速参会したいと通知しました。 |
| この通知に接したところの人々はすぐ関根方へ駆けつけ炊きだしの用意をして振る舞うということを決めました。また同町の青果屋の小板橋彦次郎氏他一軒より幾樽となくたくさんの漬け物が贈られたり、通町のこんにゃく屋ではおでんを何千串となく差し出されたり、その他白湯、茶などを用意して接待した家は数限りなくありました。 | |
| 何れも皆百姓に同情の気持を表し、親切にいろいろな便宜を与えてくれたので、一般の百姓たちの喜びはまた格別で、初め大総代の注意に三、四日分の弁当を携帯するようとのことでありました。このように歓待を受けようとは思いもよらず、意外の厚情に涙を流す者も随分見受けられました位でございます。」 |
このことについて中村先生は、「どうも、事前に炊き出しの準備をしておくようにという、高崎藩の指示があったようだ。」といいます。
その根拠とされる文書が、資料として付いていました。
| 「 | 御本領百姓共、何分困窮及難行立由二而、昨夜より御城下江相集、不容易儀二而郡奉行始夫々為利解夫々出張致候二付、此上模様次第一時御救焚出し被下候儀も可相成哉難斗間、右様相含及評議置可申旨、御勝手二申談候事」 |
(柴田家文書)
予定された2時間はあっという間に過ぎ、先生ももっといろいろお話をしたかったようですが、またの機会にゆっくりとお伺いしたいと思いました。
「高崎学検定」というものをきっかけに、たくさんの市民の方々が郷土の歴史に興味を持ち、「歴史観光都市高崎」への動きが出ることを期待してやみません。