 昨日、高松町のJT跡地で、高崎城遺跡現地説明会があるというので、行ってみた。
昨日、高松町のJT跡地で、高崎城遺跡現地説明会があるというので、行ってみた。左の絵図で、赤枠で囲った所が高崎城本丸堀の発掘調査現場である。
図をクリックして拡大すると、現在の地図と重ねてあるので分かりやすいと思う。
説明現場には、GTV(群馬テレビ)の取材クルーも来ていたので、TVでも放映されるのだろう。
風はなかったが、曇り空で寒い中、意外と大勢の人が来ていたので、驚いた。


頂いた資料によると、高崎城遺跡の発掘調査は、今回で19回目になるのだそうだ。
だが、本丸堀を発掘するのは、初めてだという。
今回の発掘により、本丸堀は幅24m、深さ約8mで、石垣を用いない「素掘り」だということが分かった。
写真にも見えるが、堀の中に木製の柵のようなものがあるが、これはおそらく、堀を埋めるために水止めをしたものだろうという。
高崎城廃城後の明治年間に描かれた高崎城絵図には、まだ本丸堀が残っているそうだから、その後、昭和初期までの間に埋められたと思われる。
今回の発掘調査で、さらに興味深い発見がされている。
高崎城の遺構の下に、さらに時代の古い溝や土器、カワラケが見つかっている。
おそらく、中世にもなんらかの構築物があり、人が住んでいたようだ。
さらにさらに、弥生時代から古墳時代と推定される溝や埴輪も見つかり、おそらく方形周溝墓、円墳があったのではないかという。
高崎は、弥生の昔から暮らしやすい所だったのかも知れない。
なお、以前「もしも、お城があったなら」で紹介した、高崎城の「三層櫓」は冒頭の絵地図で見ると、ちょうど和田橋通りの一本北の道にあったことが分かる。
ああ、それにつけても、
ここにお城があったらなぁ・・・。

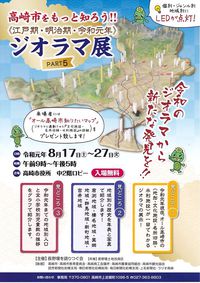

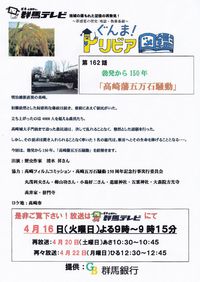

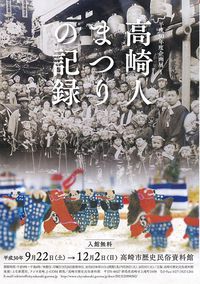
 at 2009年01月13日 15:23
at 2009年01月13日 15:23





