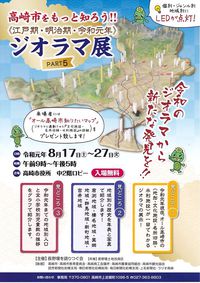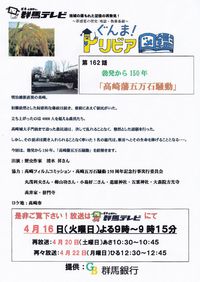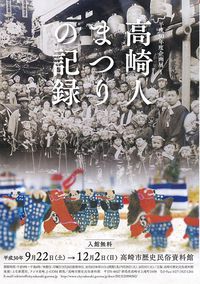「高崎新聞(TAKASAKI WEB )」に、NPOぐんま代表理事 熊倉浩靖氏の「地域力を2009年の合言葉に」という一文が掲載されている。
「高崎新聞(TAKASAKI WEB )」に、NPOぐんま代表理事 熊倉浩靖氏の「地域力を2009年の合言葉に」という一文が掲載されている。この中で、熊倉氏は「数年前から気になっている二つのこと」として、次のように述べている。
「一つは、高崎は人口増が続く数少ない地方中核都市だが、宇都宮が常に高崎以上の人口増を続けていることである。
なぜなのか。
第二は、もっと奇妙なことである。前橋の商業力である。人口減少が続いているのに、商業統計ではずっと高崎より高い売上高を続けている。前橋の方が商都。嘘だろう。」
熊倉氏は、続けて、この謎解きと、市民への提案をされているが、私はその中で興味のある言葉を見つけた。
それは「高崎は何で食べているか分かり難いといわれる・・・」というものである。
これこそ、高崎の町が今一つ伸び切れない、重要なキーワードだと思うのである。
 高崎はあまりにも多くのものを有するが故に、「こだわり」を持たない中途半端な町になっていると、私は考える。
高崎はあまりにも多くのものを有するが故に、「こだわり」を持たない中途半端な町になっていると、私は考える。例えば、「埼玉県の川越」というと何を思い浮かべるだろうか。
多くの人が、「さつまいも」「小江戸」「蔵」「時の鐘」「菓子屋横丁」などを思い浮かべるのではないだろうか。
現に、川越では「古い街並み」と「さつまいも」にこだわり抜いた町づくりで、多くの観光客(しかもリピーターが多い)を呼び寄せている。
 翻って、高崎はどうか?
翻って、高崎はどうか?代名詞はたくさんある。「商都高崎」「音楽のある街」「パスタの町」「映画の町」・・・。
名所・名物もたくさんある。「白衣観音」「城址公園」「少林山」「高崎だるま」「鉢の木」「観音最中」・・・。
上毛かるたに「関東と信越つなぐ高崎市」とあるように、交通の要でもあり、都心まで1時間という地の利もある。
あれもあるし、これもある。
しかし悲しいかな、「こだわり」が無い。
例えは適切でないかも知れないが、身体のどこも不自由でない者が、際立ったものを持ち難いのに似ている。
ハンデを背負っている人の方が、むしろ際立ったものを持っているケースが多いのである。
ハンデを背負っている人が、残った機能をフルに活かそうとする、あの「こだわり」と「努力」が、「あり過ぎる高崎」には、欠けているように思えてならない。
「広報高崎」1月1日号には、「中心市街地活性化基本計画」の概要が掲載されている。
その計画は、やはり「あれも、これも」で「こだわり」がない。
しかも、「新しい文化を創造」する方針らしく、古いものを活かそうという発想も薄い。
では、高崎は何にこだわれば良いのだろうか。
隠居の提案は、「町名」にこだわった「職人の町」づくりである。
実は、この隠居の案はもう6年前に高崎市に提案している。
「市街地活性化への提案」
その後、南銀座商店街が、それに似たコンセプトで街の風情を整備している。
昨年の「高崎ゑびす講」では、懐かしい本物のクラシックカーを通りに展示して、道行く人の目を引いていた。(中高年ばかりか、若者までも!)
同じ気持ちの人達が居たということが、嬉しくて堪らない。
「町おこしは、町残し」
大分県臼杵市後藤市長、大林宣彦映画監督の名言である。