 「三ツ寺たかっぱし公園」から北へ200mほど行った所に、壁の漆喰が剥がれた土蔵が建っていました。
「三ツ寺たかっぱし公園」から北へ200mほど行った所に、壁の漆喰が剥がれた土蔵が建っていました。何気ない風景ですが、妙に郷愁を覚えてしまうのは、いったい何故なんでしょう?
 さらに道なりに進むと、「三ツ寺公園」の大きな池、「三ツ寺堤」のたもとに出ます。
さらに道なりに進むと、「三ツ寺公園」の大きな池、「三ツ寺堤」のたもとに出ます。この「三ツ寺堤」に引き込まれている水は、新幹線トンネルの湧水なのだそうです。
日量5000トンといいますから、すごい量です。
しかし、もともとの「三ツ寺堤」は、慶安二年(1649)に造られた灌漑用の溜池です。
「三ツ寺堤」のなかった頃、この地方の土地は保水力がなく、水利にも恵まれず、日照りによる凶作に苦悩していました。
領主・安藤対馬守(高崎藩第五代藩主・安藤重信)の計らいにより、領内の農民多数動員し、乗附山の粘土を馬で運んで堤を築き、唐沢川と中島川から取水して水を貯めたと伝えられています。(三ツ寺堤由来碑より)
明治初期になると天王川からの取水に変わり、大正から昭和にかけては桜やつつじが植えられて、風光明媚な堤として賑わったといいます。
現在は、前述した新幹線トンネル(上越新幹線 榛名トンネル)の湧水を取り込んでいます。
「榛名トンネル」は、昭和五十五年(19080)に完成した、日本で6番目に長い鉄道トンネル(15.4km)です。
その工事は、脆い火山性堆積物(軽石)や大量の湧水等に悩まされ、困難を極めたようです。
榛東村では、トンネル工事による陥没事故まで起きています。
しかし、それほど苦しめた大量のトンネル湧水が、今は足門町や金古町の上水道の水源になり、この「三ツ寺堤」にも、清らかで豊かな水を提供してくれています。
ものごとの禍と福は、同じものの裏と表なんですね。
因みに、「三ツ寺」という地名は、かつて村内に「天昌寺」「長野寺」「宗慶寺(そうけいじ)」の三つの寺があったことによるとのことです。

「天昌寺」は寛永二十年(1643)の創建とありますが、檀家もなくなり無縁となったため、明治五年(1872)に廃寺となり、その跡は現在、「三ツ寺天昌寺集会所」となっています。
 集会所の奥には、如意輪観音像や薬師堂、墓地が残っていて、ここがかつて寺院だったことを偲ばせます。
集会所の奥には、如意輪観音像や薬師堂、墓地が残っていて、ここがかつて寺院だったことを偲ばせます。「長野寺」は、箕輪城主の長野氏による開基で、武田氏に焼かれて廃寺となったそうです。
場所ははっきり分かりませんが、「三ツ寺堤」の西のほとり、庚申塔が建っている辺りがそうだったという説があります。
 三つの寺の内、唯一残っているのが「三ツ寺堤」東のほとりにある、
三つの寺の内、唯一残っているのが「三ツ寺堤」東のほとりにある、「宗慶寺」です。
ただし、名前は「石上寺(せきじょうじ)」となっています。
「石上寺」は、もともと箕輪にあったお寺で、箕輪城主・井伊直政とともに、高崎城下の鞘町に移ってきます。
お堀端の「時の鐘」があったお寺です。
一方、三ツ寺にあった「宗慶寺」も、箕輪城主・長野業政の二男・業盛が開基した寺ですが、後に「石上寺」の末寺となります。
そして、明治二十四年(1891)に、「石上寺」が高崎から三ツ寺に移転してきて、吸収合併されたという訳です。
ところで、かつてこの地域は「堤が岡村」の一部でした。
この地名にも、面白い話が伝わっています。
この地域は水利に恵まれなかったために、大小いくつもの溜池(堤)が築かれていましたが、「雨がなければ、堤が、岡のようになる」ということからきているそうです。
いやー、地名って、歴史の無形文化財ですね。
近頃流行りの「ひらがな地名」は、後々どんな歴史・文化を伝えてくれるのでしょうか。
【三ツ寺堤・石上寺】
【天昌寺跡】





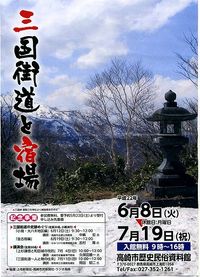


 at 2010年01月03日 11:39
at 2010年01月03日 11:39





