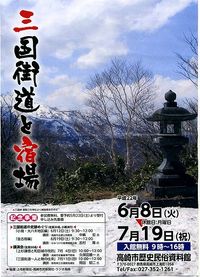前回、「中野秣場(まぐさば)騒動」のきっかけは、明治六年(1873)に「中野秣場」が国有地になったことだと書きました。
国有地になったことで、野付、札元、札下という不平等な「秣札」制は廃止され、入会の村々は公平に「秣場」を利用することができるようになりました。
秣税についても、「秣場」全体に掛けられた168円98銭を、82ヶ村の戸数や人口などにより割り付けて、各村々が負担することとなりました。
これだけ見れば、実に平等な制度になったと言えましょう。
 ところが、明治八年(1875)、地租改正のための測量が行われた際、「中野秣場」3100町歩の内、松ノ沢村の飛び地47町歩だけが、なぜか松ノ沢村の官有地として登録されます。
ところが、明治八年(1875)、地租改正のための測量が行われた際、「中野秣場」3100町歩の内、松ノ沢村の飛び地47町歩だけが、なぜか松ノ沢村の官有地として登録されます。
これが、後々の騒動の火種となる訳です。
松ノ沢村では、その47町歩の土地を「部分木地」※1として県に申請します。
明治十二年(1879)に許可を取得した松ノ沢村は、「部分木地」への植林を始めるとともに、その周辺に標杭を立てて、他村民の立ち入りを禁止したのです。
そのことを知ってか知らずか、明治十三年(1880)七月、行力村の農民が「部分木地」に侵入し、松ノ沢村民に咎められて警察沙汰になるという事件が起こります。
また同じ月に、今度は浜川村の農民が「部分木地」の雑木を伐採して、松ノ沢村民に捕えられて没収されるという騒ぎもありました。
この事件が、日頃から松ノ沢村に対して不快感を抱いていた、他村の農民たちの気持ちに火を付けてしまいます。
松ノ沢村内の官有地は、もともと数百年の昔から「中野秣場」の入会地であり、松ノ沢村だけが独占すべきものではない、という気持ちが一気に噴出したのです。
白川の河原に集結した数千人の農民は、松ノ沢村の「部分木地」に入って手当たり次第に伐採を始めます。
高崎警察署の鎮撫にもかかわらず、この騒動は5日間も続きました。
松ノ沢村を除く81ヶ村の代表たちは、浜川の来迎寺に集合して話し合いをしますが、その時、大総代に選出されたのが、42歳の真塩紋弥です。
真塩らは、棟高村の県会議員・志村彪三の仲裁で、松ノ沢村との間に和解約定書を交わすことに成功しました。
約定書には、
(1)松ノ沢村の「部分木地」を官有地にしたことを取り消す。
(2)「部分木地」に植えた木は役所の許可が下り次第、伐採する。
などの項目があり、これで従前通りの「秣場」になるはずでした。
ところが、(2)項の役所の許可がいつまで経っても下りてきません。
そうこうしている内に、松ノ沢村は先の和解を破棄し、逆に他の村々を訴える挙に出たのです。
ここに、騒動はまた再燃してしまいます。
明治十四年(1881)三月、81ヶ村の代表たちは福島村の金剛寺に集結し、「部分木地」の伐採強行を決議します。
これに対し県は、警察ばかりか軍隊の出動まで準備して、鎮圧に乗り出します。
真塩紋弥と福島村・青木亀吉は東京の内務省に駆け込み、事件の真相を内務卿・松方正義に直訴しようとしますが、待ち構えていた警視庁により逮捕されてしまいます。
熊谷裁判所前橋支庁は、真塩紋弥に対し凶徒嘯聚(しょうしゅ)※2罪で懲役二年半、讒謗律(ざんぼうりつ)※3違反で禁獄三十日の判決を言い渡します。
そうして真塩紋弥が投獄されたのが、あの岩鼻監獄でした。
その後、三ツ寺村民による保釈請願もあって、明治十七年(1884)刑期途中で保釈されます。
 獄を出た真塩紋弥は、再び教育の道に戻るものの徐々に家運傾き、明治四十三年(1910)鬼石町に移住し、翌、明治四十四年(1911)74歳の生涯を閉じます。
獄を出た真塩紋弥は、再び教育の道に戻るものの徐々に家運傾き、明治四十三年(1910)鬼石町に移住し、翌、明治四十四年(1911)74歳の生涯を閉じます。
墓は、生まれ故郷の稲荷台、真塩家墓地の一角に隠れるように建っており、なかなか見つけることができませんでした。
ロウセキで文字をなぞってみたら、台石に「門人之を建つ」と刻まれていました。
国有地になったことで、野付、札元、札下という不平等な「秣札」制は廃止され、入会の村々は公平に「秣場」を利用することができるようになりました。
秣税についても、「秣場」全体に掛けられた168円98銭を、82ヶ村の戸数や人口などにより割り付けて、各村々が負担することとなりました。
これだけ見れば、実に平等な制度になったと言えましょう。
 ところが、明治八年(1875)、地租改正のための測量が行われた際、「中野秣場」3100町歩の内、松ノ沢村の飛び地47町歩だけが、なぜか松ノ沢村の官有地として登録されます。
ところが、明治八年(1875)、地租改正のための測量が行われた際、「中野秣場」3100町歩の内、松ノ沢村の飛び地47町歩だけが、なぜか松ノ沢村の官有地として登録されます。これが、後々の騒動の火種となる訳です。
松ノ沢村では、その47町歩の土地を「部分木地」※1として県に申請します。
明治十二年(1879)に許可を取得した松ノ沢村は、「部分木地」への植林を始めるとともに、その周辺に標杭を立てて、他村民の立ち入りを禁止したのです。
※1. | 部分林:国有林野に、契約によって国以外の者が造林し、 その収益を国と造林者が分けあう林地。(大辞林) |
そのことを知ってか知らずか、明治十三年(1880)七月、行力村の農民が「部分木地」に侵入し、松ノ沢村民に咎められて警察沙汰になるという事件が起こります。
また同じ月に、今度は浜川村の農民が「部分木地」の雑木を伐採して、松ノ沢村民に捕えられて没収されるという騒ぎもありました。
この事件が、日頃から松ノ沢村に対して不快感を抱いていた、他村の農民たちの気持ちに火を付けてしまいます。
松ノ沢村内の官有地は、もともと数百年の昔から「中野秣場」の入会地であり、松ノ沢村だけが独占すべきものではない、という気持ちが一気に噴出したのです。
白川の河原に集結した数千人の農民は、松ノ沢村の「部分木地」に入って手当たり次第に伐採を始めます。
高崎警察署の鎮撫にもかかわらず、この騒動は5日間も続きました。
松ノ沢村を除く81ヶ村の代表たちは、浜川の来迎寺に集合して話し合いをしますが、その時、大総代に選出されたのが、42歳の真塩紋弥です。
真塩らは、棟高村の県会議員・志村彪三の仲裁で、松ノ沢村との間に和解約定書を交わすことに成功しました。
約定書には、
(1)松ノ沢村の「部分木地」を官有地にしたことを取り消す。
(2)「部分木地」に植えた木は役所の許可が下り次第、伐採する。
などの項目があり、これで従前通りの「秣場」になるはずでした。
ところが、(2)項の役所の許可がいつまで経っても下りてきません。
そうこうしている内に、松ノ沢村は先の和解を破棄し、逆に他の村々を訴える挙に出たのです。
ここに、騒動はまた再燃してしまいます。
明治十四年(1881)三月、81ヶ村の代表たちは福島村の金剛寺に集結し、「部分木地」の伐採強行を決議します。
これに対し県は、警察ばかりか軍隊の出動まで準備して、鎮圧に乗り出します。
真塩紋弥と福島村・青木亀吉は東京の内務省に駆け込み、事件の真相を内務卿・松方正義に直訴しようとしますが、待ち構えていた警視庁により逮捕されてしまいます。
熊谷裁判所前橋支庁は、真塩紋弥に対し凶徒嘯聚(しょうしゅ)※2罪で懲役二年半、讒謗律(ざんぼうりつ)※3違反で禁獄三十日の判決を言い渡します。
そうして真塩紋弥が投獄されたのが、あの岩鼻監獄でした。
その後、三ツ寺村民による保釈請願もあって、明治十七年(1884)刑期途中で保釈されます。
※2. | 嘯聚:呼び集めること |
※3. | 讒謗律:明治8年(1875)明治政府によって公布された言論統制令。自由民権運動の隆盛に伴う政府批判を規制するため、人を誹謗する文書類を取り締まった。(大辞泉) |
 獄を出た真塩紋弥は、再び教育の道に戻るものの徐々に家運傾き、明治四十三年(1910)鬼石町に移住し、翌、明治四十四年(1911)74歳の生涯を閉じます。
獄を出た真塩紋弥は、再び教育の道に戻るものの徐々に家運傾き、明治四十三年(1910)鬼石町に移住し、翌、明治四十四年(1911)74歳の生涯を閉じます。墓は、生まれ故郷の稲荷台、真塩家墓地の一角に隠れるように建っており、なかなか見つけることができませんでした。
ロウセキで文字をなぞってみたら、台石に「門人之を建つ」と刻まれていました。
(参考図書:「群馬町誌」「群馬県史」「騒動」)
【真塩紋弥の墓】