 旧中山道と国道406号の分去れから、「藤川橋」まで戻ります。
旧中山道と国道406号の分去れから、「藤川橋」まで戻ります。橋を渡って左折し、再び「藤川」に沿って歩きます。
車もほとんど通らず、流れの音を楽しみながら落ち着いて歩けます。
 150mほど行くと、右手奥の高台にお寺の屋根のようなものが見えます。
150mほど行くと、右手奥の高台にお寺の屋根のようなものが見えます。ちょっと気になったので、行ってみることにしました。

道なりに坂を上っていくと、「姫宮公園」となっています。
「姫宮」、何だか好奇心をそそられる名前です。
 赤城山がきれいに望める墓地に、お堂が一つ建っていました。
赤城山がきれいに望める墓地に、お堂が一つ建っていました。「姫宮観音堂」と書かれています。
 お堂の前に建つ「姫宮観音の由来」によると、少林山達磨寺の末寺として開山されたようですが、「姫宮」という名前の謂れについては書かれていません。
お堂の前に建つ「姫宮観音の由来」によると、少林山達磨寺の末寺として開山されたようですが、「姫宮」という名前の謂れについては書かれていません。後で調べてみると、建立者の梁瀬次郎氏の言として、「梁瀬家の先祖は甲州武田家の遺臣で、武田勢が戦いに敗れた時、豊岡村に逃げて土着した。」という話しがあるので、あるいは山梨の「姫宮神社」と何か関係があるのでしょうか。
梁瀬次郎氏は、輸入自動車販売の老舗・「梁瀬自動車」(現・株式会社ヤナセ)の二代目社長です。
次郎氏は生まれつき病弱で吃音があったために、初代社長の父・長太郎氏からは大変厳しくあたられたといいます。
その体験が、土地を寄付し、「観音堂」を建立し、碑文の「当地の皆様の幾久しいご平安をお祈りする」という優しさを生んだのかも知れません。
 墓地の一角に、「梁瀬孫太郎夫妻之墓」という、ひときわ大きな墓石が建っています。
墓地の一角に、「梁瀬孫太郎夫妻之墓」という、ひときわ大きな墓石が建っています。梁瀬孫太郎氏は、「上毛かるた」で有名な船津傳次平の弟子として、「石並べ苗床」の研究と普及に大きな功績を残した人物です。
 「石並べ苗床」は、路傍の草が石に接しているところだけ背丈が高いことに気付き、苗床に応用したものです。
「石並べ苗床」は、路傍の草が石に接しているところだけ背丈が高いことに気付き、苗床に応用したものです。豊岡では、碓氷川や烏川から平らな石を拾い集めて苗床に並べ、特産の「豊岡胡瓜」の栽培に利用したそうです。
安政六年(1859)豊岡村の小百姓の次男として生まれた孫太郎氏は、幼い頃から父と共に未明から夕刻遅くまで野良仕事に精出し、夕食が済むと縄ないに藁仕事という毎日でした。
やがて、口減らしのために分家に養子に出されますが、本家と分家の両方の仕事をこなすという、過酷な労働の日々が続きます。
働いても働いても抱え続ける多くの借財に耐えきれず、20歳になった孫太郎氏はついに東京へ出て行ってしまいます。
股引に筒袖の野良着に草鞋履きという姿で、3日かけて歩いて行ったといいます。
その行方を探し、借財を立て替えてくれた近所の人の恩に報いるため、孫太郎氏は農業に専念することを決意します。
明治十八年(1885)高崎の大信寺で船津伝次平の農談会が行われ、孫太郎氏もこれに参加していました。
この時、最前列に座って熱心に講義を聞く姿を傳次平に認められ、師弟関係が結ばれたのだそうです。
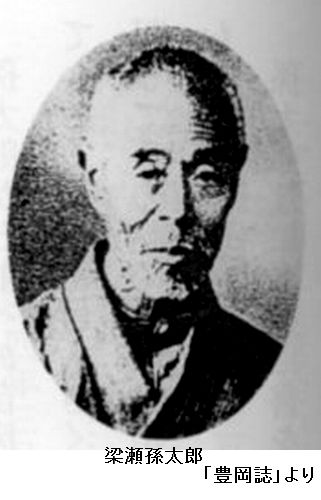 篤農家として有名になってからも、いつも質素な身なりで倹約に努めた孫太郎氏の人となりは、次のようなエピソードで伝えられています。
篤農家として有名になってからも、いつも質素な身なりで倹約に努めた孫太郎氏の人となりは、次のようなエピソードで伝えられています。4月~9月は4時、10月~3月は5時に起きる、これを生涯実行し、朝起きると中山道を通る馬の糞を拾い集めて、これを堆肥に使う。
馬のわらじは短く切って炭俵に詰めておき、溜ると高崎の左官へ持って行って1俵2銭で売る。
しかし、ただの倹約家と違うのが孫太郎氏です。
左官へ売った代金は、27歳の時からすべて「奉仕筒」と書いた竹筒に入れておき、58歳まで貯めた820円余りの金で田畑1町3反、梨畑と山林9反1畝20歩を購入します。
その山林に「青年山」と名付けて地元の青年団に寄付し、青年団はそれを開墾して杉・桧・松などを植えました。
それらの木は、昭和二十二年(1947)村民の手によって切り出され、新制中学校の建築用材として使われたということです。
孫太郎氏がつくった13カ条の人生訓から、いくつかを拾ってみましょう。
| 一、 | 農業は聖人君子を気取って行うことができる。 |
| 一、 | 儲けることばかり考えては百姓は成り立たない。 |
| 一、 | 人間は働けば不味いものと病気はない。 |
| 一、 | 経済の元は一家病気をしないことである。 |
| 一、 | 嫁を呉れるならその家の堆肥を見よ。 |
| 一、 | 被服と住家は飾るべからず、飾れば他人にそねまれる。 |
いやー、深い。
ということで、今日はここまでにいたしましょう。
(参考図書:「豊岡誌」「高崎の散歩道」)
【姫宮公園】













